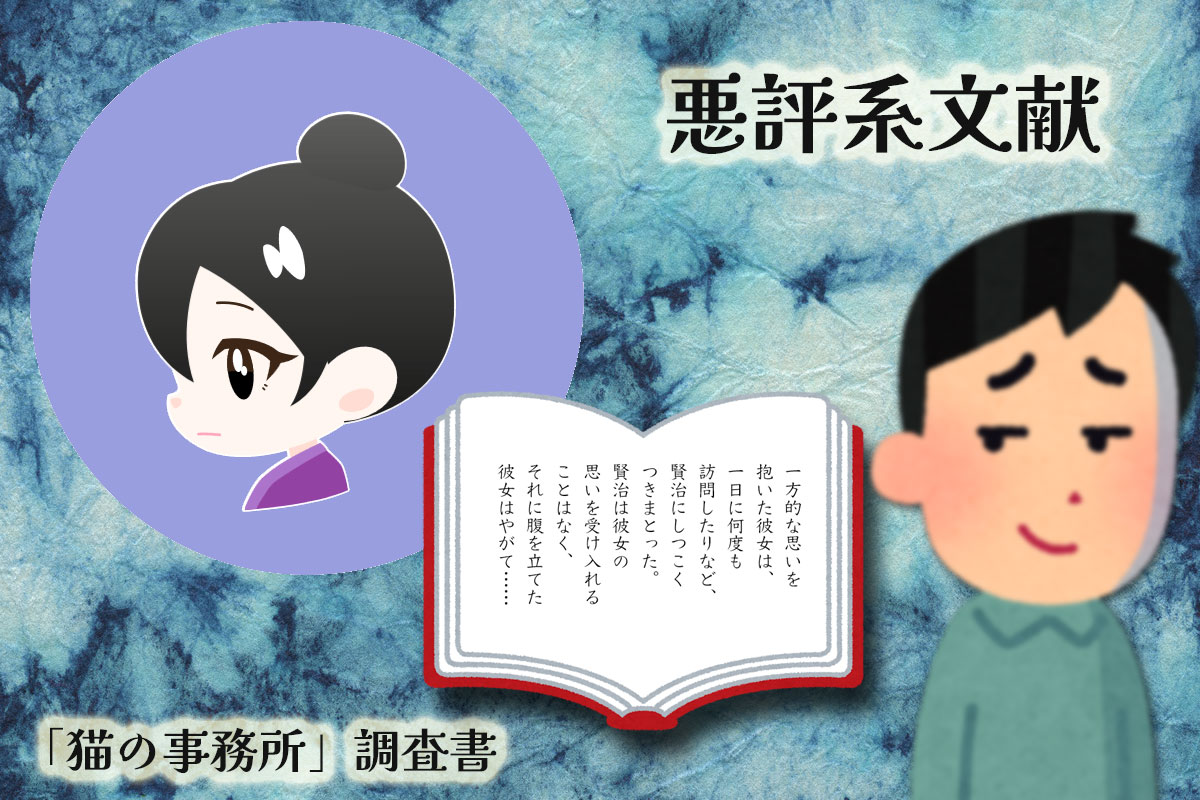前記事で、儀府文献「やさしい悪魔」のまとめの一節にある「この人のことを悪魔のように見たり云ったりするのはやめたい」「(内村康江に)私はとにかく拍手をおくりたい」という言葉に対し「空々しさとずるさにまみれていて開いた口が塞がらない」と述べましたが、当記事ではそう考えてしまう理由をもうひとつ述べていきたいと思います。
「やさしい悪魔」の締めから約15ページ先に、以前の記事でも取り上げた「火の島の組詩」という章が収録されています。

この章は、内村康江を「聖女のさました人」と称し、賢治がCという女性に出会いCの住む伊豆大島へ赴いたことを知ってどういうことを考えどういう行動を取ったのかを記している内容だったね。
該当箇所を再び引用します。
Cが賢治を訪ねて花巻へきたこと、賢治がC兄妹の招きに応じて大島へいったことー普通ならばだいたいこの辺の動きで断念し、おとなしく身をひきそうなものだが、聖女のさました人(引用者注・内村康江のこと)は逆だったらしい。相手のCは、自分のように働いて食べるのが精いっぱいだという職業婦人ではなくて、名も富も兼ねそなえた恵まれた美しい女性であるということがシャクだった。それにもまして、賢治がCに奔ったのは、どっちがトクかを秤にかけて、打算からやったことだと邪推し、恋に破れた逆恨みから、あることないこと賢治の悪口をいいふらして歩くという、最悪の状態に陥ったのだと考えられる。あれほど温厚で、人のためなら自己犠牲も辞さなかった賢治が、冤を雪ぐ、というほど大げさなものではなかったにせよ、 わざわざ関登久也の家まで出かけてこの件に触れたのは、よくよく腹にすえかねたからだったと思われる。彼女は不純な女だと傍人に漏らしたというのも、こんな事情に由るものだったに相違ない。
儀府成一「宮沢賢治 ●その愛と性」 芸術生活社 1972(昭和47)年

…つまり、「この人のことを悪魔のように見たり云ったりするのはやめたい」と言ったそばから「この人のことを悪魔のように見たり云ったり」しているわけなんだね…。
「この章に登場する「聖女のさました人」は内村康江とは別の人のことを言っているのではないか」という指摘を頂きそうですが、残念ながら儀府は「やさしい悪魔」で賢治の「聖女のさましてちかづけるもの…」で始まる殴り書きを引用し「それは内村康江のことを書いている」と断言してしまっているのです。該当部分を以下に引用します。
聖女のさましてちかづけるもの たくらみすべてならずとて
いまわが像に釘うつとも 乞ひて弟子の礼とれる
いま名の故に足をもて われに土をば送るとも
わがとり来しは たゞひとすじのみちなれや(略)例の『雨ニモ負ケズ』のある同じ手帳に書き込まれている一篇で、詩というよりもメモとも見えるほど軽いものだが、よく読めば首尾一貫した詩であることがわかる。しかもその内容となると、チェホフの短篇をたった八行にちぢめたのかと思うほど、濃いものだ。相手は——内村康江だ。若気の至りから、相手も未婚、自分も独身であることを忘れて、蒲団というとんでもない贈りものをして、すでに賢治に想いを寄せていた女心を、余計狂奔させたというあの喜劇と悲劇をつきまぜたような悲劇のヒロインだ。「聖女のさまして」は、彼女がクリスチャンであったことと、その反語として、「悪女」または「悪魔」を対置させているのである。

「内村康江だと思われる」じゃなくて「内村康江だ」と自信満々に断言しちゃってる。儀府文献での内村康江に関する記述全てに言えることだけど、こんなの単なる儀府の感想に過ぎないじゃん。
15ページほど前で「この人のことを悪魔のように見たり云ったりするのはやめたい」と書いておきながら、その発言をすっかり忘れたかのように「内村康江という人は、思い込んだら話が通じなくなり行動も選ばなくなる危ない人」と読者に思わせるような記述をしている「火の島の組詩」。
この章を読んだ後改めて「やさしい悪魔」の締めの部分を読むと、言葉のひとつひとつに透けて見えていた空々しさとずるさをより強く感じるのです。

まあ「それこそあなた達の感想に過ぎない」と言われてしまえばそれまでだけど…。とにかく私と管理人は愚問は承知の上で儀府に問いたいです。
「あなたの『内村康江のことを悪魔のように見たり言ったりするのをやめたい』という言葉は本物なのですか?」