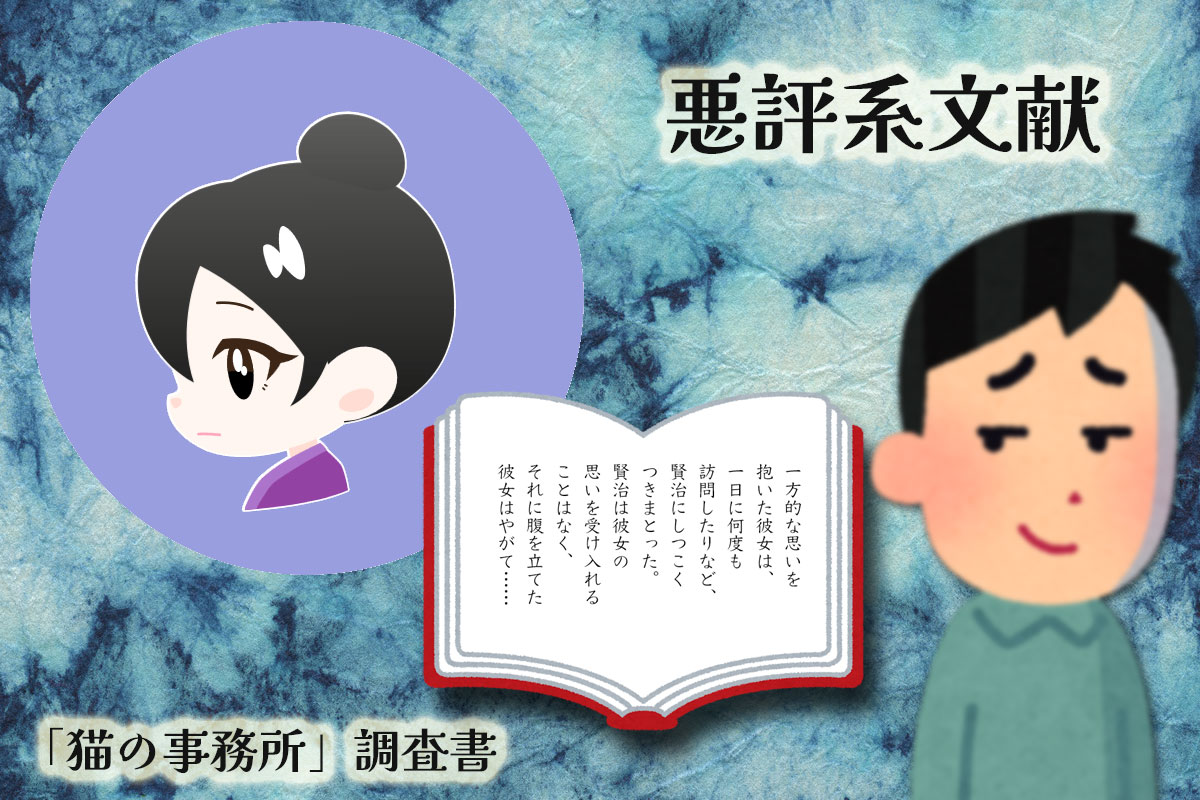1926(大正15)年秋〜1928(昭和3)年夏にかけての森荘已池の「動向」が判明しましたがひとまずそれは脇に置いて、引き続き森の文献「宮沢賢治と三人の女性」「高雅な和服姿の”愛人”」より気になるところを抜き出し、意見・感想を述べていきます。
すれ違った女性の「様子」
森荘已池が「和服姿の女性」とすれ違った時の場面をそれぞれ引用します。
二十二三才の女の人で和服だった。派手ではなかったが、上品な柄の着物だった。
森荘已池「宮沢賢治と三人の女性」1949(昭和24)年
私はその顔を見て異常だと直感した。目がきらきらと輝いていた。そして丸顔の両頬がかっかっと燃えるように赤かった。全部の顔いろが小麦いろゆえ、燃える頬はりんごのように健康な色だった。かなりの精神の昂奮でないと、ひとはこんなにからだ全体で上気するものではなかった。歓喜とか、そういう単純なものを超えて、からだの中で焔が燃えさかっているような感じだった。私はそれまで、この女の人についての知識はひとかけらも持ち合わせていなかった。 ——が、宮沢さんのところを訪ねて帰ってきたんだなと直感した。 私は半身、斜にかまえたような恰好で通り過ぎた。 私はしばらく振り返って見ていたが、彼女は振り返らなかった。
羅須地人協会が旧盆に開かれたその年の秋の一日であった。そこへ行くみちで、私はひとりの若い美しい女の人に会った。その人は、そのころからはやり出した、もみじ色の、はでではあるが高雅な気分のある和服姿であった。その着物と同じように、ぱっと上気した顔いろに、私はびっくりした。少し前まで興奮した「時間」があったのだなと私は思った。
森荘已池「ふれあいの人々 宮沢賢治」>17ページ「高雅な和服姿の”愛人”」1980(昭和55)年
まず気になるのは「道ですれ違っただけの人の様子をとても詳しく描写している」という点です。
読者の皆さんにお聞きしたいのですが、道ですれ違った人のことを(たとえその人がちょっと目立つ雰囲気を醸し出していていたとしても)ここまで細かく覚えているでしょうか?
一目見てすぐ分かるのは「性別・大体の年代・色黒か色白か・服装・服の色や柄の雰囲気」といった大まかなものくらいで「目がきらきらと輝いていた」「頬が燃えるように赤かった」などよほど近い距離でしっかり見ていなければ分からないでしょう。
森荘已池とその女性はそんなに近い距離をすれ違ったのでしょうか?
普通向こうから人が来ると分かればそれなりの距離を取るのではないでしょうか。
次に「からだ全体で上気・からだの中で焔が燃えさかっているような感じ」という点については、森にこう問いたいです。
「そんなこと、すれ違っただけでどうやって分かるんですか?」
すれ違っただけの人が「上気しているか・興奮しているか」なんて、その人が何か声でも上げない限り分からないと思います。
この和服姿の女性は「ひとけのない、付近に藪や雑木林のある田舎道を一人で歩いている時に、見ず知らずの男性に目の輝き・顔色までしっかり分かるほど近くに寄って凝視されていた」ということになります。彼女はさぞ気味悪く感じたことでしょう。
さらには「少し前まで興奮した「時間」があったのだな」などと勝手な想像まで抱いていたというわけです。女性の端くれとして率直に言わせて頂くと、この言葉に対しては「キモい」の一言に尽きます。
あと一目瞭然な相違点として気になるのは「着物は派手だったのか派手ではなかったのか」
この一点だけで「森荘已池、賢治を訪問する途上で上気した様子の和服姿の女性とすれ違う」という話の信憑性が格段に薄くなると思います。
森荘已池は「高雅な和服姿の”愛人”」を書くにあたり「すれ違った女性」のイメージに尾ひれをつけたかったのでしょうが、まずご自身の著書をチェックする習慣をつけられるべきだったと思います。
何度も読み返す必要がある文章
「高雅な和服姿の”愛人”」には後日談的な一文があります。以下に引用します。
この女の人が、ずっと後年結婚して、何人もの子持ちになってから会って、色々の話を聞き、本に書いた。
森荘已池「ふれあいの人々 宮沢賢治」>17ページ「高雅な和服姿の”愛人”」1980(昭和55)年
この人の娘さんが、亡き母の知人に「古い日記に母が『宮沢賢治は、私の愛人』と書いております」と話したという。
この引用部分、一読して皆さんはどう受け取りましたか?
おそらくこのように受け取ったのではないでしょうか。
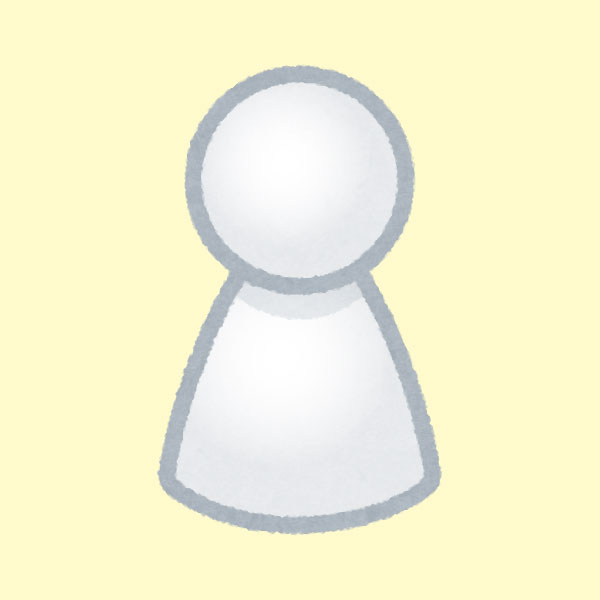
森荘已池は後年、結婚し母親になった「高雅な和服姿の女性」に会い、色々話を聞いて本に書いた。彼女の娘も「亡き母の知人へ、母が古い日記に『宮沢賢治は、私の愛人』と書いていたことを話した」と森荘已池に明かした。
ところがよく読んでみるとそうではないことが分かります。この文章には場面が2つあるんですね。
1.森荘已池は後年、結婚し母親になった「高雅な和服姿の女性」に会い、色々話を聞いて本に書いた 2.さらに時は経ち「高雅な和服姿の女性」亡き後、彼女の娘が女性の知人に「古い日記に母が…」と話したということを、何者かが森荘已池に聞かせた つまり:女性の娘→女性の知人→(第三者)→森荘已池
前記事でも言及しましたが、この「高雅な和服姿の”愛人”」という文章、全体的に誤解を招くような構成になっていて、複数回読み返す必要があります。
「高雅な和服姿の女性」が古い日記に『宮沢賢治は、私の愛人』と書いていたという「女性の娘」の話は何者かからの又聞きであり、その「何者か」が「和服姿の女性母娘・その知人とどういう関係性であるか」を森荘已池は一切書いていません。
その日記は果たして実在するのでしょうか? 森荘已池の創作の可能性も充分考えられます。
森荘已池は「高雅な和服姿の女性」の娘・知人も「人の日記の内容を他言する」ような問題ある人物に仕立て上げることで「高雅な和服姿の女性」を徹底的に貶めようとしているのではないか…と考えてしまいます。
「和服姿の女性」=高瀬露さん?
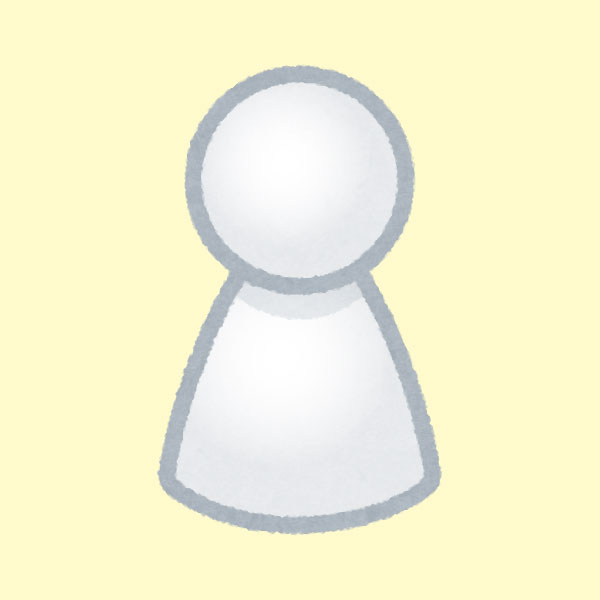
ところでその和服姿の女性の話、高瀬露さんに関係あるの?
と考えた方もおられると思います。
確かに「宮沢賢治と三人の女性」「高雅な和服姿の”愛人”」共にこの和服姿の女性が何者であるかの記述はありません。もしかしたら露さんとは別の、賢治に関わりがあった女性だったという可能性も考えられそうですが…。
「高雅な和服姿の”愛人”」が収録されている書籍「ふれあいの人々 宮沢賢治」の20ページに「カレー・ライスを固辞」という文章があります。「高雅な和服姿の”愛人”」から連載3回分先にあたるこの文章、賢治と露さんの通説のひとつである「ライスカレー事件」がテーマになっているものですが、その文頭にはこんな一節があるのです。
宮沢賢治の伝記映画を作ることになったら、もっとも生き生きとした画像に表現できるのは、 羅須地人協会時代であろう。女人関係となったら、「T女登場」になろう。
森荘已池「ふれあいの人々 宮沢賢治」>20ページ「カレー・ライスを固辞」1980(昭和55)年
T女が、紅葉のように上気して帰った次の日のこと。私は井戸端で顔を洗おうとしていた。水を汲(く)んだ茶腕(わん・ママ)に、賢治がパラリと入れたものがある。それは青い松の葉の数本であった。水に浮いて、底に影を落とした。
「女の人が来たでしょう。あなたが、とまったでしょう。 女の人が、とまったことになるんです。」
森荘已池は、賢治を訪ねる途上ですれ違った女性はイニシャルがTになる名であることを明かしています。露さんは苗字も名前も「T」というイニシャルになります(Takase Tsuyu)。
この連載の3年前である1977(昭和52)年、「校本宮澤賢治全集」第14巻で高瀬露さんの名前が公表されました。これによって多くの賢治愛好家は「賢治の元によく出入りしていたイニシャルがTの女性=露さん」と認識してしまったのです。
仮に森荘已池が「露さんではない、別のTという女性」を記していたとしても、このような印象がついてしまった以上「露さんとは無関係の話」と言うことは出来ないと思います。
あるネットスラングを思い浮かべてしまう
まずは上田哲さんの「「宮澤賢治伝」の再検証(二)―<悪女>にされた高瀬露―」より以下の部分を引用します。
森は彼女に逢ったのは、<一九二八年の秋の日><下根子を訪ねた>(注 下根子とは賢治の羅須地人協会である)その時、彼女と一度あったのが初めの最後であった。その後一度もあっていないことは直接わたしは、同氏から聞いている。
上田哲「「宮澤賢治伝」の再検証(二)—<悪女>にされた高瀬露—」1996(平成8)年
森荘已池は、和服姿の女性=高瀬露さんとはすれ違っただけで、本に書けるほどの会話すらしたことがなかったと自ら明かしているのです。
ただ、前記事に記した通り羅須地人協会活動期間中の森荘已池は「東京在住、その後重病を患い長期入院していた」ということが判明しています。ならば和服姿の女性=高瀬露さんも顔すらあわせたことがない、つまり森は上田さんに嘘の証言をしたということです。
そして「高雅な和服姿の”愛人”」で書いた「この女の人が、ずっと後年結婚して、何人もの子持ちになってから会って、色々の話を聞き」という部分も嘘、和服姿の女性が日記に書いたという文章・それを人に言いふらす問題ある人物はやはり全て森荘已池の創作だったということになります。
このエッセイは朝日新聞岩手版で連載されていたというせいで、「アサヒる」というネットスラングが頭に浮かんでしまいました。
森荘已池は「和服姿の女性=T女=高瀬露さん」関連…どころか、羅須地人協会活動中の話において「アサヒる」行いに及んでいるのです。