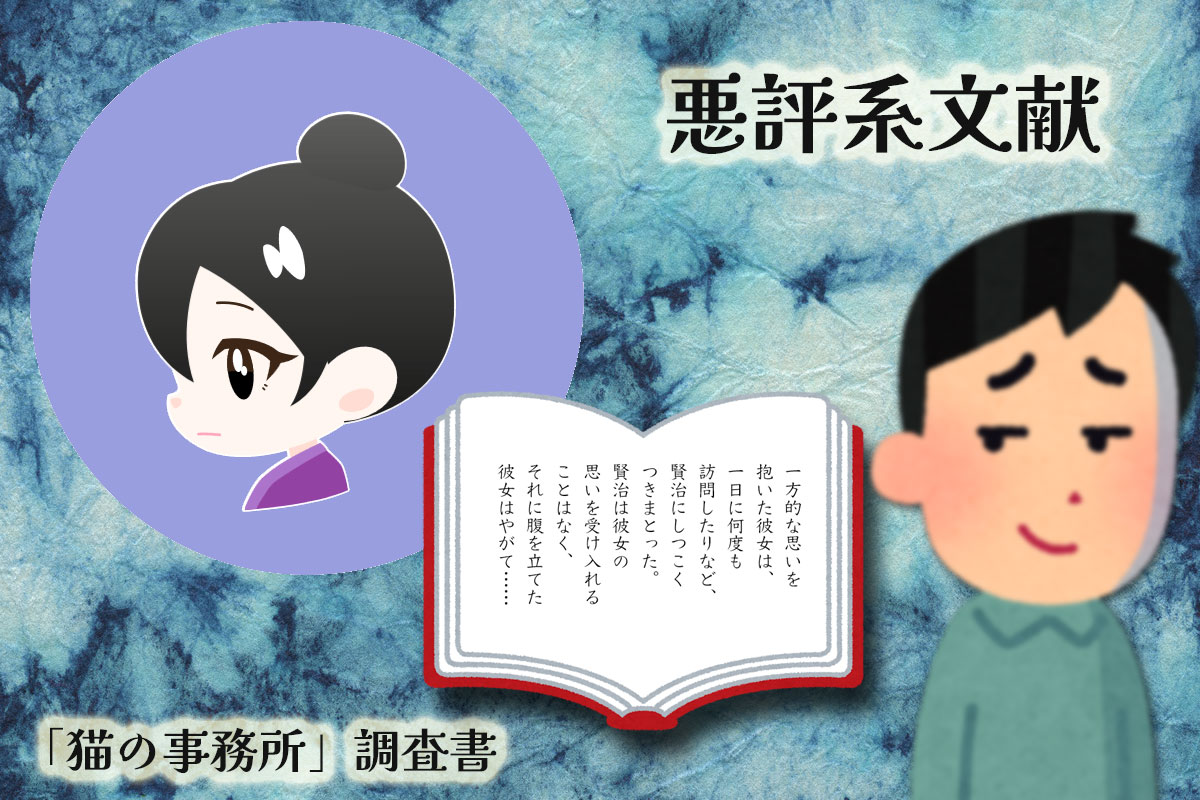1926(大正15)年秋〜1928(昭和3)年夏にかけての森荘已池の「動向」が判明し、文献の記述が虚構である可能性が出てきました。ですがひとまずそれは脇に置いて、引き続き森の文献「宮沢賢治と三人の女性」「高雅な和服姿の”愛人”」より気になるところを引用し、意見・感想を述べていきたいと思います。

この記事で取り上げる「気になるところ」は「森が語る『すれ違った際の和服姿の女性の様子』」です。
両文献より「森荘已池が和服姿の女性とすれ違った時の場面」をそれぞれ引用します。
ふと向こうから人のくる気配だった。私がそれと気づいたときは、そのひとは、もはや三四間向うにきていた。(湿った道と、そのひとのはいているフェルトの草履が音をたてなかったのだ。)私は目を真直ぐにあげて、そのひとを見た。二十二三才の女の人で和服だった。派手ではなかったが、上品な柄の着物だった。私はその顔を見て異常だと直感した。目がきらきらと輝いていた。そして丸顔の両頬がかっかっと燃えるように赤かった。全部の顔いろが小麦いろゆえ、燃える頬はりんごのように健康な色だった。かなりの精神の昂奮でないと、ひとはこんなにからだ全体で上気するものではなかった。歓喜とか、そういう単純なものを超えて、からだの中で焔が燃えさかっているような感じだった。私はそれまで、この女の人についての知識はひとかけらも持ち合わせていなかった。 ——が、宮沢さんのところを訪ねて帰ってきたんだなと直感した。 私は半身、斜にかまえたような恰好で通り過ぎた。 私はしばらく振り返って見ていたが、彼女は振り返らなかった。
森荘已池「宮沢賢治と三人の女性」1949(昭和24)年
羅須地人協会が旧盆に開かれたその年の秋の一日であった。そこへ行くみちで、私はひとりの若い美しい女の人に会った。その人は、そのころからはやり出した、もみじ色の、はでではあるが高雅な気分のある和服姿であった。その着物と同じように、ぱっと上気した顔いろに、私はびっくりした。少し前まで興奮した「時間」があったのだなと私は思った。
森荘已池「ふれあいの人々 宮沢賢治」>17ページ「高雅な和服姿の”愛人”」1980(昭和55)年
両引用で気になるのは「道ですれ違っただけの人の様子をとても詳しく描写している」という点です。道ですれ違った人のことをここまで細かく覚えているものなのでしょうか?

その人がちょっと目立つ雰囲気を醸し出していたとしても、すぐ分かるのは「性別・大体の年代・色黒か色白か・服装・服の色や柄の雰囲気」といった大まかなものくらいだよね。
「目がきらきらと輝いていた・頬が燃えるように赤かった・からだ全体で上気・からだの中で焔が燃えさかっているような感じ」など、よほど近い距離でしっかり見ていなければ分からないことです。ですが森とその女性はそこまで近い距離にいたわけではありません。「三四間向う」の距離から「その顔を見て異常だと直感した」と記しているのです。

1間は約1.8メートルか。となると3〜4間は約5.4〜7.2メートル…こんな距離じゃ目の輝きや頬の赤みなんて分からないよ。すれ違う間際でも森はともかく女性の方が距離を取ろうとするだろうから、森から近づかない限り分からないままだよね。
この和服姿の女性は「ひとけのない、付近に藪や雑木林のある田舎道を一人で歩いている時に、見ず知らずの男性に目の輝き・顔色までしっかり分かるほど近くに寄って凝視されていた」ということになります。

こう書くとなんだか気味が悪いね。さらには「少し前まで興奮した「時間」があったのだな」などと勝手な想像まで抱いていたんだから、これじゃ森のほうが「不審者」になっちゃうよ。
最後に一目瞭然な相違点として気になるのが「着物は派手だったのか派手ではなかったのか」。
先発の「宮沢賢治と三人の女性」では「派手ではなかったが、上品な柄の着物」とし、後発の「高雅な和服姿の”愛人”」では「もみじ色の、はでではあるが高雅な気分のある和服姿」としているのです。
この「着物のイメージが180度違う」という点だけでも「賢治を訪問する途上で上気した様子の和服姿の女性とすれ違った話」の信憑性は格段に薄くなると思います。

森は後発の「高雅な和服姿の”愛人”」を書く際に「すれ違った女性のイメージ」に尾ひれをつけようとしたんだろうけど、その前に先発の「宮沢賢治と三人の女性」の内容をチェックしようとは思わなかったのかな。…言いにくいけど、その辺りどうも「いい加減」という感じがするなぁ。