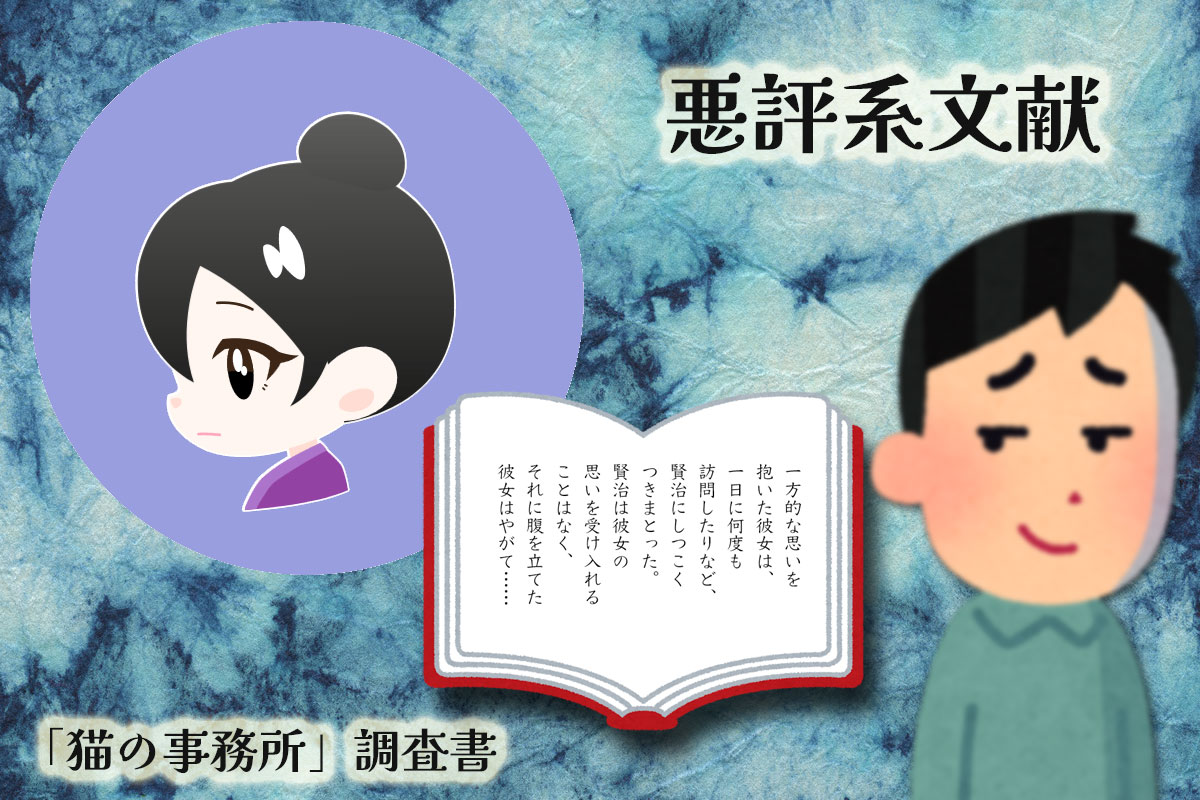森荘已池文献の露さんに関した記述で必ず出てくるのが「独居自炊している賢治を訪ねる途中ですれ違った和服姿の女性」。これまでなんとなく読んできたけど、この機会に読み返してみたら…明らかにおかしいと感じる部分があるんだよ。
このエピソードを「宮沢賢治と三人の女性」と「高雅な和服姿の”愛人”」から引用します。両文献の収録書籍は以下の通りです。
- 宮沢賢治と三人の女性:津軽書房出版「宮沢賢治の肖像」1974(昭和49)年
- 高雅な和服姿の”愛人”:熊谷出版印刷部出版「ふれあいの人々 宮沢賢治」1988(昭和63)年
まずは「宮沢賢治と三人の女性」から。
宮沢賢治が、花巻農学校教諭を依願退職して、花巻町下根子の宮沢家の別荘を改築し、そこに農耕自炊の生活をはじめたのは大正十五年春であるが、その年八月には「羅須地人協会」を設立した。発表式は田舎では誰もが仕事を休む旧盆の十六日であった。
(中略・女性教員=露さんの登場から賢治の忌避行動まで)
一九二八年の秋の日、私は下根子を訪ねたのであった。
(中略)
ふと向こうから人のくる気配だった。私がそれと気づいたときは、そのひとは、もはや三四間向うにきていた。
(湿った道と、そのひとのはいているフェルトの草履が音をたてなかったのだ。)
私は目を真直ぐにあげて、そのひとを見た。
二十二三才の女の人で和服だった。派手ではなかったが、上品な柄の着物だった。(中略)
畑のそばのみちを通り過ぎ、前方に家が見えてきた。二階に音がした。しきりにガラス窓をあけている賢治を見た。彼は私に気がつくとニコニコッと笑った。明るいいつもの顔だった。私たちは縁側に座を占めた。彼はじっと私の心の底をのぞきこむようにして
森荘已池「宮沢賢治と三人の女性」 文献の初出:1949(昭和24)年
「いま、とちゅうで会ったでしょう?」
といきなりきいた。
「ハァー」
と私が答え、あとは何もいわなかった。少しの沈黙があった——。
「おんな臭くていかんですよ。」
彼はそういうと、すっぱいように笑った。

羅須地人協会の設立が「その年(大正15年)八月」としっかり書かれていて、森が賢治を訪ねたのが「一九二八年の秋」つまり昭和3年の秋ってことね。
次に「高雅な和服姿の”愛人”」より。
それは、紅葉がほんとうに美しい、この秋一番という好天の日だった。何軒か、老杉と紅葉する大樹の混こう林の中に、大きな農家が何軒かあった。
羅須地人協会が旧盆に開かれたその年の秋の一日であった。
そこへ行くみちで、私はひとりの若い美しい女の人に会った。その人は、そのころからはやり出した、もみじ色の、はでではあるが高雅な気分のある和服姿であった。
その着物と同じように、ぱっと上気した顔いろに、私はびっくりした。少し前まで興奮した「時間」があったのだなと私は思った。大正十四年夏、この協会ができた時、お訪ねしたいと手紙を出すと、今はとても忙しいから、秋においでなさいと返事があった。駄(だ)客、閑客の類だから、ヒマになったらおいで、ということだと、素直に受け取った。
きょうが初めての未知の家への途上で、ばったりと、この女人に会ったのである。
(中略)
二階建てのりっぱな別荘が、向こうに現れ、二階に動く人影があった。近づくと、声が降ってきて、主は賢治その人だった。前のように白くはなくて、小麦色になった笑顔だった。
二階のガラス戸を、しきりに音させてあけている。
二階と下とで「女の人と、いま会ったんでしょう」「ハア、すぐそこで」「女くさくていかんのです。川風に吹きはらわせています」などと、会話した。(後略)
森荘已池「ふれあいの人々 宮沢賢治」>17ページ「高雅な和服姿の”愛人”」 文献の初出:1980(昭和55)年

こっちは、出来事が前後しててちょっと読みにくいな…注意して読まないと混乱してしまいそう。
この文献によると、森荘已池が賢治を訪ねたのは羅須地人協会が開かれた年の秋。「大正十四年夏、この協会ができた時」つまりその直前には訪問したい旨の手紙を賢治に送り、秋に来てくれという返事を受け取っていることになります。

大正14年を西暦にすると…1925年。
…そう、ここ! おかしいと思うのはここなんです!