
高瀬改め小笠原露さんは1939(昭和14)年12月と1940(昭和15)年9月、賢治を偲ぶ短歌を数首詠んでいます。
露さんの短歌を初めて目にしたのは2003(平成15)年頃のことで、短歌のセンスなど全く持っておらず「詠めるだけでもすごい」と思っている私が抱いた感想は「どの歌も賢治に対する敬愛が溢れている」でした。
それと同時に「露さんは一方的な思いが破れたことを恨んで賢治を中傷して歩くようになった」という通説に疑問を抱き始めたのです。
それから露さんの人柄や彼女が受けた仕打ちを詳しく知ることになりました。
その上でこの短歌を見ると本当に切ないような遣る瀬ないような思いが沸き起こるようになり、彼女のことを知れば知るほどそれは強くなってしまいました。
時には鼻の奥がつんと痛くなってくるほどです。
当記事では露さんの短歌に対する細かい感想を述べたいと思います。
1939(昭和14)年12月13日
この日に詠まれた短歌は5首。
賢治を偲ぶ機関誌「イーハトーヴォ」第4号(1940年2月21日発行)に「露草」の雅号で「賢治先生の霊に捧ぐ」と題されて掲載されたものです。
「君逝きて七度迎ふるこの冬は早池の峯に思ひこそ積み」

露さんの、賢治に対する思いが凝縮された一首だと感じました。
温かくもありほろ苦くもある思いを胸に抱きながら、薄く涙を浮かべて早池峰山を見つめる露さんの姿を想像してしまいます。
この一首だけでも「露さんが賢治に一方的な思いを押し付け、それが破れたら賢治を中傷して歩くようになったなど嘘なんじゃないか」と微かにでも思えるのではないかと思います。
「ポラーノの広場に咲けるつめくさを早池の峯に吾は求めむ」

「ポラーノの広場」にて、お祭りのある広場(ポラーノの広場)を照らす明かりとして登場する「つめくさ」。「賢治の童話にちなんだ歌」というお題が出たのでしょうか?
露さんはきっと賢治の童話を丁寧に読んでおり、「ポラーノの広場」を特に好んでいたのかなと思いました。
早池峰山に幻想的な明かりを灯しながら咲く「つめくさ」に囲まれて微笑む、さながら「ポラーノの広場」のヒロイン(?)・ロザーロのような露さんを想像してしまいます。
「オツペルに虐げられし象のごと心疲れて山に憩いぬ」

「オツベルと象」が登場。こちらもお題に沿って詠まれた一首なのでしょうか。
時期的には違うでしょうし、「心疲れ」たのも別のことでと思いますが、つい「賢治とのことで火のないところに煙を立てられたことに関して詠んだのだろうか」と考えてしまいます。
露さんは長きにわたり「賢治研究界」という「オツペル」に虐げられ続けてきました。
敬虔なクリスチャンだった露さんは、この仕打ちを「自分が担うべき苦しみ」として反論・弁解をすることはありませんでしたが、それでもやはり「苦しいです。サンタマリア」と心で溢すことも沢山あっただろうと思います。
露さんの精神力の強さに脱帽するばかりです。
「粉々のこの日雪を身に浴びつ君がみ徳の香によひて居り」

個人的に一番好きな短歌です。
初見時に「なんて美しい短歌なんだろう」と感じました。特に「粉々の」「雪」と「君がみ徳の香」の言葉の組み合わせが本当に綺麗だと思います。
賢治の行いに感じ入った時と粉雪が結びつくような思い出があったのでしょうか。
粉雪の舞う中、少し涙ぐみつつも微笑みを浮かべて空を見上げる露さんの姿が浮かんできます。
「ひたむきに吾のぼりゆく山道にしるべとなりて師は在すなり」

露さんの、宮沢賢治に対する深い敬愛が良く現れた短歌だと感じました。
賢治との交流があった時に抱いたかもしれない淡い感情もネガティブな感情も全て「敬愛」という形に昇華され、賢治との交流もいい思い出になっていると感じられ、こちらも何だか胸が温かくなります。
思いが届かなかった相手を恨んで中傷するような人間には(いくら外面を取り繕っていたとしても)詠めない歌だと思います。
1940(昭和15)年9月1日
この日詠まれた短歌は4首。
当時の露さんの勤務校である遠野尋常高等小学校で開催された「賢治の集ひ」にて詠まれたものです。
20日後の9月21日に発行された機関誌「イーハトーヴォ」第10号に掲載されています。
「師の君をしのび来たりてこの一日心ゆくまで歌ひ語りぬ」
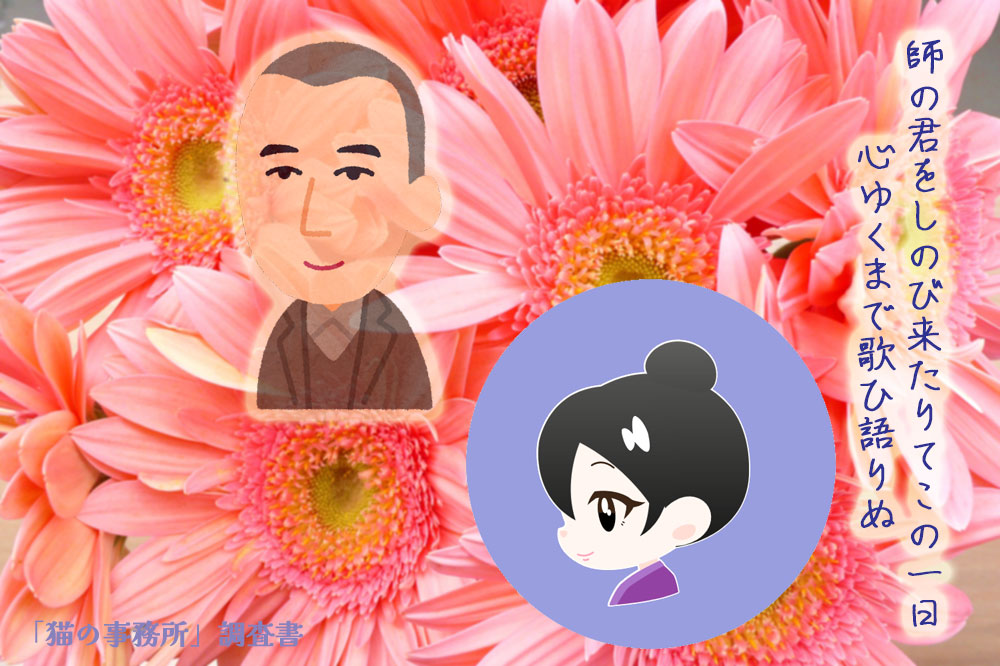
この日の最初の一首でしょうね。
「心ゆくまで歌ひ語りぬ」という言葉に、露さんがこの集いを楽しみにしていた様子や賢治との思い出を本当に大切に思っている様子が手に取るように感じられ、微笑ましく思ってしまいます。
「教え子ら集ひて歌ひ語らへばこの部屋ぬちにみ師を仰ぎぬ」
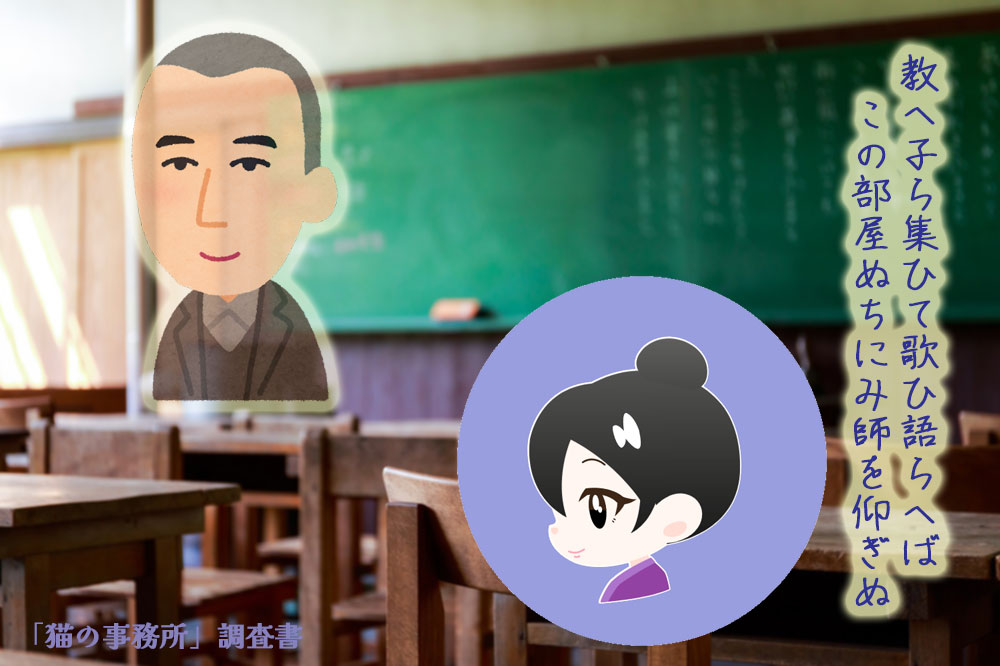
「賢治の集い」には賢治の教え子だった人が数人出席しています。彼らと短歌を詠って賢治の思い出を語り合っているうちに、賢治の元に通っていた頃のような雰囲気になってきたのでしょう。
この短歌からは「賢治の元に通っていた時のことは露さんにとって良い思い出になっている」こと、更に「露さんは賢治の教え子たちから悪く思われていたわけではない」ことが読み取れると思います。
そして、この短歌を詠んでいる「その時」も本当に楽しい時間だったのでしょうね。
「いく度か首をたれて涙ぐみみ師には告げぬ悲しき心」
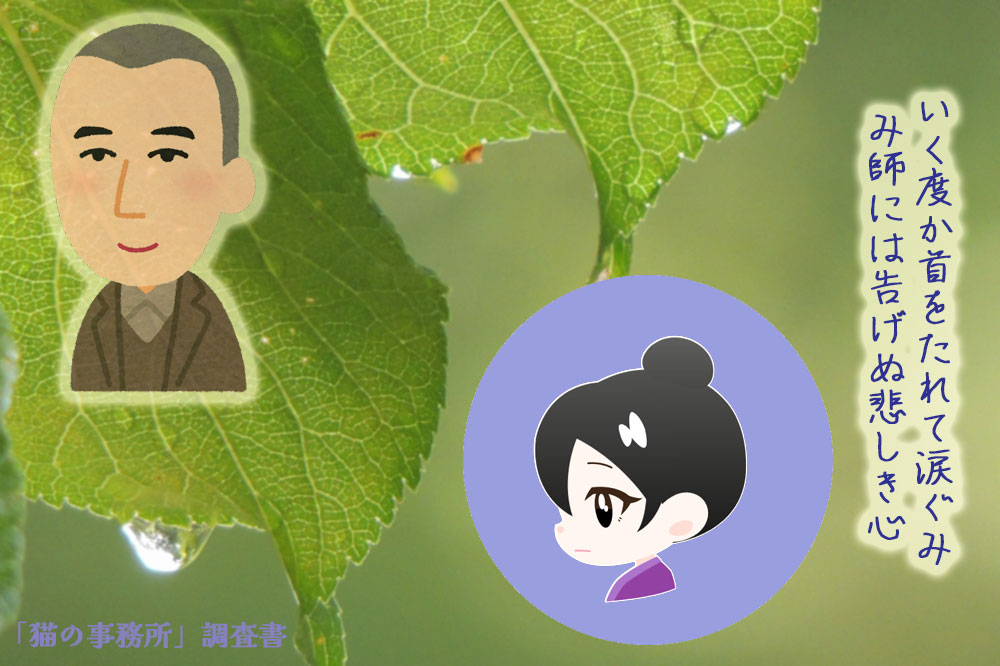
「首をたれて涙ぐみ」「悲しき心」という言葉の印象が強いですが、賢治への恨み節のような歌ではないと思います。
露さんはそんな出来事も既に「大切な思い出」に昇華しており、「宮沢先生との間にはこんなこともあった」と穏やかに思い起こしている状態を詠っている一首だと感じます。
「うつむいて涙ぐむほど悲しい思いをしたのはどの出来事か」を探ることはせず、短歌を詠んだその時の露さんの思いを素直に受け取っておきたいですね。
「女子のゆくべき道を説きませるみ師の面影忘れなくに」

露さんの人柄・彼女の賢治に対する姿勢や考え方が詰まった一首だと思います。
「ひたむきに吾のぼり行く…」よりも強く、本当に賢治を「師」として考え、仰いでいる様子が感じ取れます。もしかすると賢治と知り合って割と早い段階で賢治を「師」として考え、接していたのでは…と思ってしまいます。
そして「ひたむきに吾のぼり行く…」同様、通説で言われている「相手に一方的に思いを押し付ける、それが破れたら相手を中傷して歩く」ような人柄だったら、どんなに表面を取り繕っていても詠めない歌だと思います。
ふと「もし賢治がこの歌を目にしたらどういう思いを抱くのだろう」と考えてしまいました。
私が賢治の立場であれば「羅須地人協会活動当時の彼女に対する振る舞い」を思い返し、自らを恥じたり悔やんだりすると思います。
「短歌を詠んだ事実」から見えること
露さんの短歌を読み返すたびに「賢治と露さんの関係や露さんの人柄は通説で言われているようなものではないことへの確信」と「なぜ彼女がこのような悪評を被せられなければならなかったのかという疑問」が強くなります。
また「短歌を読んだりその意味を考えたりする以前に、このことで『露さんは賢治やその関係者から疎まれるような行動はとっていない』と分かるのでは?」ということが見えてきました。
それは、
「露さんはきちんと賢治の訃報を受け取り、賢治に関する集まりや機関誌(賢治の教え子も参加している)にも参加できているという事実がある」
ということです。
露さんが本当に通説で言われているような問題行動をとり賢治やその関係者から疎まれていたなら、賢治の訃報を耳にすることは出来たとしても賢治に関する集まりや機関誌に参加することは出来なかった(いわゆる「出禁」扱いになっていた)のではないでしょうか。
露さんの通説を信じている方にも露さんの通説を目にして日が浅い方にも、ご一考頂ければと思います。



