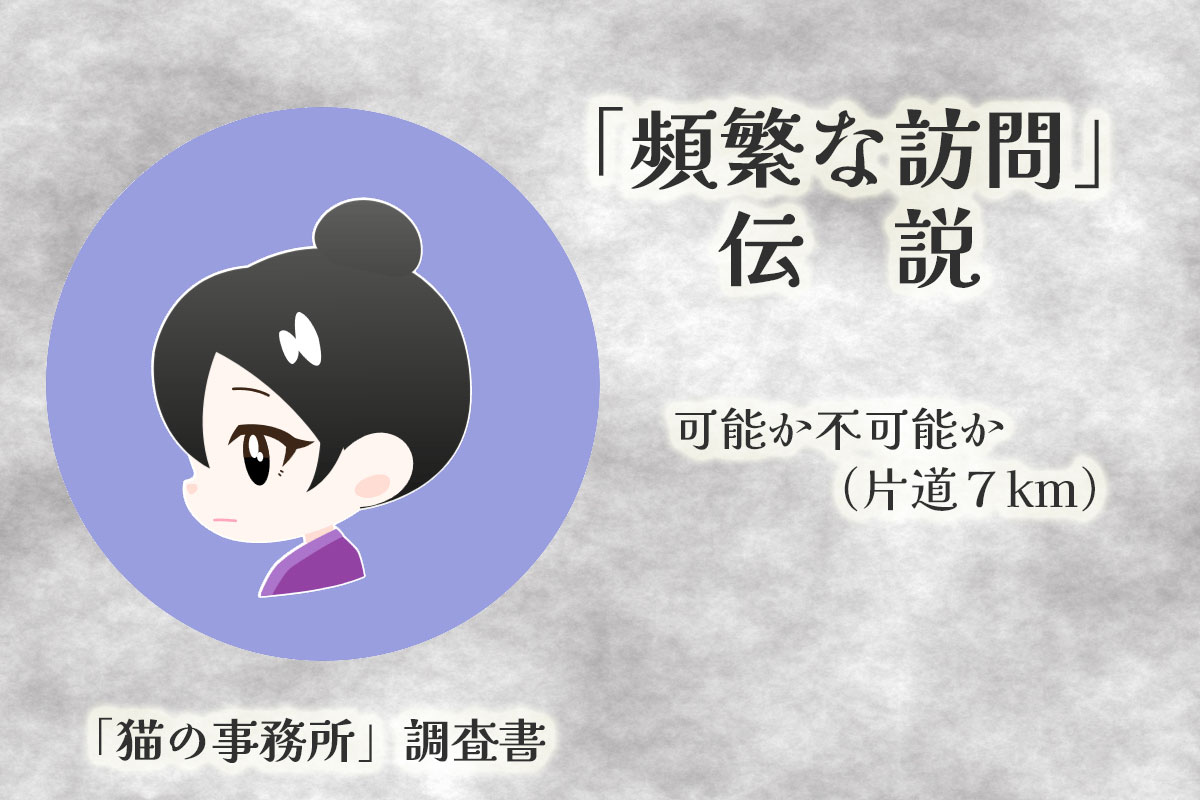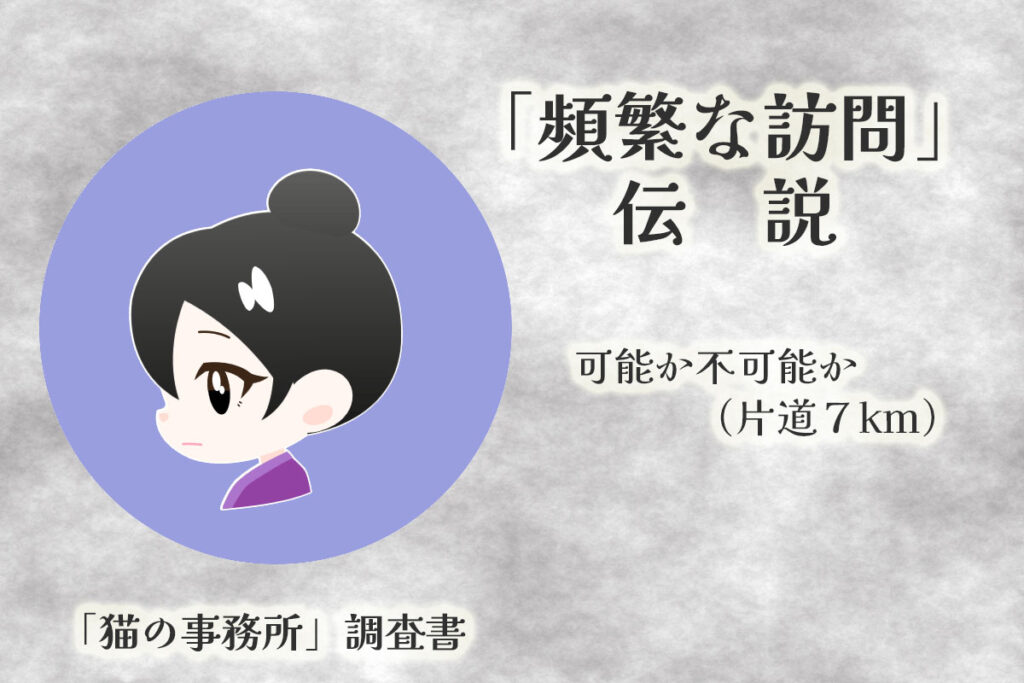
羅須地人協会活動期間中の高瀬露さんの勤務校は、下根子桜の宮沢賢治の住まいから約7〜8キロの距離があることが分かりました。
そんな距離から、しかもお勤めを持つ身で「賢治が辟易するほどの頻繁な訪問」が出来るのかを当記事で考えていきたいと思います。
勤務校から賢治宅までルート検索してみた
森荘已池は「花巻の西方の村で小学校の教員をしている女の人」と記しており、その女性=露さんが西方の村=湯口村に住んでいるのか別の町から通っているのかはこれだけでは分かりません。
ともあれ、小学校の教員をしている人が「1日に2回も3回も」やってくるのであれば行動の起点は勤務校ということになります。
露さんの勤務校である宝閑尋常小学校(当時の所在地の推定地点)から下根子桜の賢治の住まいまで徒歩で向かうとどのくらいの時間がかかるのか、Googleマップでルート検索してみました。以下に貼付します。
だいたい2時間近くかかるようですね。1926(大正15)年〜1927(昭和2)年は道の状態も服装も歩きやすいものではなかったでしょうし、上記地図ほど道の数も多くなかったでしょうから、さらに時間がかかっていたのではないでしょうか。
片道の所要時間2時間・お昼休みを利用しての訪問・お昼休みの開始12時00分・賢治宅で過ごす時間を1時間と仮定して考えると以下のようになります。
学校出発12時00分・賢治宅到着14時00分・賢治宅出発15時00分・学校到着17時00分
…午後の授業を丸々放棄してしまうことになりますね。
当時軽便鉄道が通っていたとのこと
旧ブログでこの話を取り上げた際「また花巻を訪れた時は宝閑尋常小学校跡地から宮沢家別宅跡地(「雨ニモマケズ」詩碑)まで歩き所要時間を計測してみたい」などと述べました。
その後読者の方より宝閑尋常小学校の正しい位置と共に「当時は軽便鉄道が通っていた」との情報を頂き(感謝!)、コメント拝見時その存在を全く知らなかった私は早速軽便鉄道、後の花巻電鉄軌道線について調べ、改めて記事を書いたということがありました。
下根子桜の賢治宅の最寄り駅は「西公園」、宝閑尋常小学校の最寄り駅は頂いたコメントによると6つ先の「一本杉」という駅だった1ようです。しかし、賢治宅から西公園駅までの距離は約2.5キロ・徒歩35分ほど、宝閑尋常小学校から一本杉駅までの距離は約3.5キロ・徒歩50分ほど。さらに両駅間の所要時間や電車がやってくる間隔も考慮すると、徒歩よりほんの少し時間が短くなるだけと予想されます。
花巻電鉄の情報は旧ブログで取り上げた2007(平成19)年当時はWikipediaしか頼るところがなかった記憶がありますが、現在は廃線跡を散策し写真を掲載されているウェブサイトさんが沢山出てきます。一本杉駅(跡)周辺も露さんが宝閑尋常小学校に勤務していた頃の様子をある程度想像することができ、感慨深い気持ちになります。
当時の彼女の住まいから可能性を考える
さて、当時の露さんは「花巻の西方の村」に住んでいたのでしょうか、それとも別の町に住んでいたのでしょうか。
筑摩書房発行の「【新】校本宮澤賢治全集 第十六巻(下)補遺・資料 年譜篇」には「賢治が独居自炊をはじめた下根子桜の近く、向小路に住んでいた」とあり、上田哲さんの「「宮澤賢治伝」の再検証(二)ー<悪女>にされた高瀬露ー」に引用されている教員履歴書にも「稗貫郡花巻町向小路」と記載されています。
「向小路」は古い地名で、現在は花巻市桜町2丁目のあたりになるそうです。下根子桜の賢治の住まいへは徒歩で10〜15分程度くらいでしょうか。花巻電鉄軌道線の最寄り駅は同じく西公園駅になり、そこまでの所要時間は賢治宅からそう変わりはないでしょう。
自宅から通勤していたとしたら、まず徒歩で西公園駅へ行き電鉄乗車、一本杉駅で降車し勤務校まで徒歩ということになります。
Wikipediaの花巻電鉄ページによると1934(昭和9)年12月当時軌道線の1日の運行本数は6往復半・全線の所要時間は1時間34分〜1時間36分・駅数21とのこと。
露さんが賢治・羅須地人協会に関わっていた1926(大正15)年〜1927(昭和2)年も運行本数・所要時間・駅数は変わりないと仮定して上記データをもとに通勤時間を計算します。
軌道線1駅間の所要時間をざっくり計算すると約4〜5分、これをもとに西公園駅から一本杉駅までの所要時間を計算すると約24〜30分になります。これに自宅から駅・駅から学校までの移動1時間25分をプラスすると、片道の所要時間は1時間49分〜1時間55分ほど。以下に各所要時間を整理します。
高瀬家〜西公園駅(徒歩):約35分 西公園駅〜一本杉駅(電鉄):約24〜30分 一本杉駅〜宝閑尋常小学校(徒歩):約50分 合計所要時間:1時間49分〜1時間55分(109分〜115分) ※高瀬家〜宝閑尋常小学校(徒歩):約2時間(120分)
予想通り徒歩での所要時間よりほんの少し短くなったという程度、通勤時間としては割と長めですね。勤務校での先生方の朝礼が8時とすれば遅くとも朝4時頃に起床し、5時50分頃には自宅を出発しないと間に合いません。
朝はとても賢治宅を訪ねる余裕はなさそうです。退勤後も駅到着と電車のタイミングが合わなければ(あるいは電車の時間に合わせて勤務校を出発する?)賢治宅を訪れるどころじゃない時間になりそうです。
いや、それ以前に…1日6本程度の運行なのに上記出勤時間に都合が良い電車があるのでしょうか。花巻電鉄利用の自宅通勤すら非現実的に思えてきました。
上田哲さんは「「宮澤賢治伝」の再検証(二)ー<悪女>にされた高瀬露ー」で「(露さんは)向小路二十七番地の実家から通学していたのである」と記し、徒歩での通勤であるような表現をしていますが、それも「賢治宅への頻繁な訪問」同様現実的ではありません。
でも1920年代に教職員住宅みたいなものはなかっただろうし、やっぱり花巻電鉄を使って通勤していたのかな…と長年考えていましたが、ブログ「みちのくの山野草」様によると「当時の露さんは勤務校付近で下宿をしていた」とのこと(記事「高瀬露は当時下宿していたことが判明」)。下宿という可能性が思い浮かばなかった自分の無知を恥じております。
この点においては森荘已池の「花巻の西方の村に住んでいる」ような表現が正しかったというわけですね。どちらにしても「頻繁な訪問」は不可能なことに変わりはありませんが…。
おそらく土曜日の授業終了後に花巻電鉄を利用して実家に帰り、日曜日の夕方頃に同じく花巻電鉄を利用して下宿先に戻ったのでしょう。体調不良など状況によっては帰らない週末もあったかもしれません。
どれもこれも無理のある「設定」だった
徒歩で通うにしろ軽便鉄道を使うにしろ、また遠くに住んでいようが近くに住んでいようが「小学校教員という職を持つ人」が「1日に何度も訪れる」など現実的ではないことが分かりました。
本当にそんなことをすれば「午前もしくは午後の授業を丸々放棄する・頻繁に欠勤する」ことになってしまいます。当時の宝閑尋常小学校はどんな様子だったのか、手持ちの資料から引用します。
同校(引用者注・宝閑尋常小学校)大正十三年の学校一覧を見ると、児童は男八八、女八五の計一七三名で、それを校長、年輩の男先生、若い女先生即ち高瀬の三人で受持ち、複式学級で、彼女はずっと一、二年を受持っている。校務は校長が庶務、男先生が教務、女先生が衛生を担当、現在でいえば養護教諭を兼ねていた。
米田利昭「宮沢賢治の手紙」230〜231ページ 大修館書店 1995年
ざっくり計算すると1学年28〜29人、複式学級だから最多で58人受け持つことになります。露さんはそれに併せて「保健室の先生」も担当しているのです。そして先生方は露さんを含め3人しかおられません。
こんな状態で「職務放棄」すればたちまち「おかしな先生がいる」という噂が流れるでしょうし、現場からも問題視されるでしょう。懲戒免職になってもおかしくありません。
また「1日に何度も訪れる」ということ自体、たとえ無職であっても効率の悪い行いではないでしょうか。いちいち行って戻って…を繰り返すより長時間居座ったほうが時間を有効に使えるし「押しかけ女房的行為」としてもこちらの方が自然です。
以下のような「設定」にしておけば綻びが出なかったのではないでしょうか。
- 「花巻の西方の村に住んでいる小学校教員の女性」が「休日の度に朝早くやってきて日が暮れるまで居座る」
- 「近隣に住んでいる無職の女性」が「毎日やってきて長時間居座る」
「逸話」としてはインパクトに欠けるでしょうが、どちらも賢治に精神的負担を与える行いであることには変わりありません。
真実は上記ほど極端ではなく「露さんは日曜午前中に賢治を訪ね長くともお昼過ぎ頃まで滞在していた(但し毎週ではない)、それに対し賢治が(勝手に)負い目を感じるようになった」のではないかと思います。
- 鉛温泉方面1つ先にある「二ツ堰」という駅も当時の宝閑尋常小学校所在地に近いようですが、当ブログでは頂いたコメントに従って記事を作成させて頂きました ↩︎