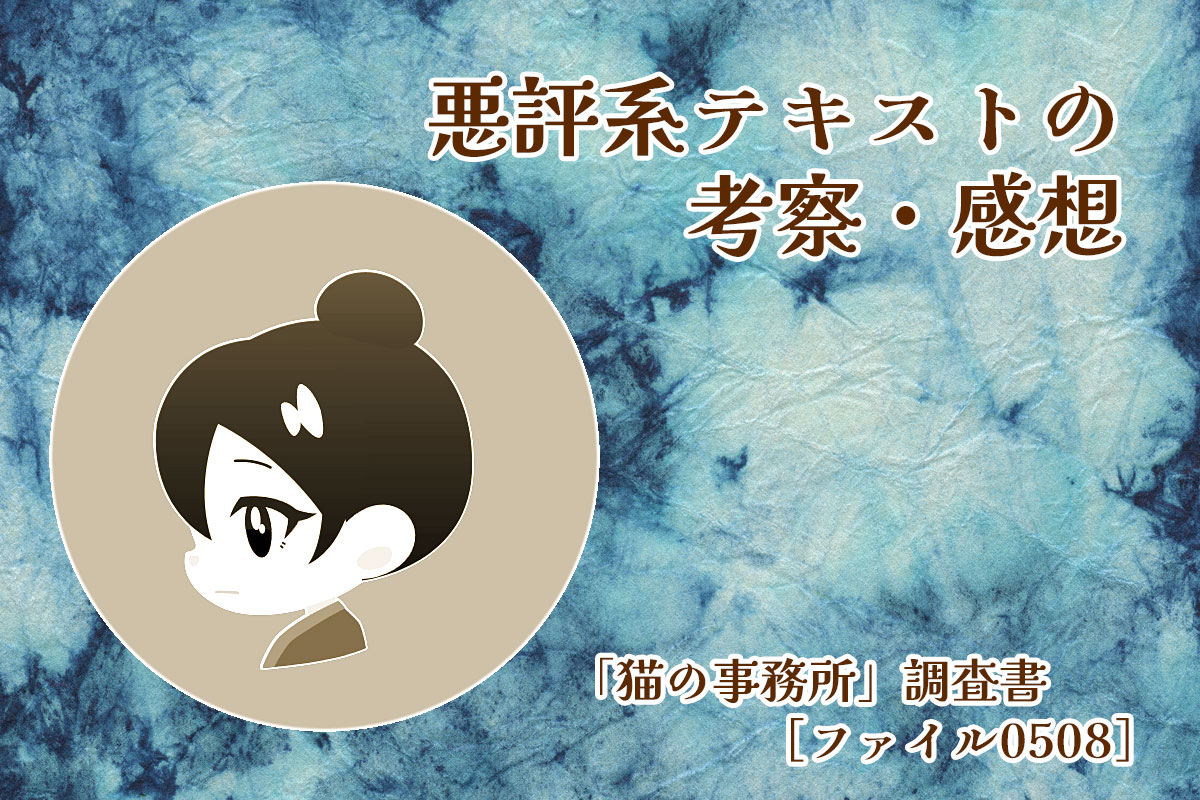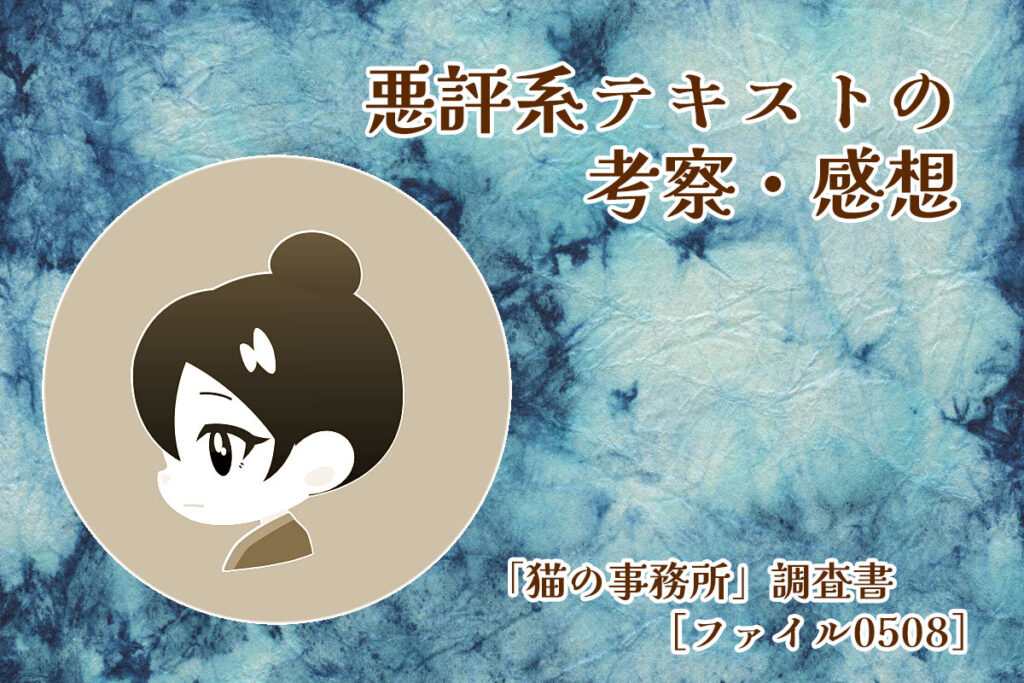
森荘已池氏がご自身の著書・コラムで記した高瀬露に関する記述。当エントリでは両者に見られる相違点を比較し、考察したいと思います。
まず一つ目の相違点は森氏が羅須地人協会を尋ねたという時期。
「三人の女性」では、様々な場所で指摘されていますが、賢治が病を得て自宅療養をしている時期であるはずの1928年すなわち昭和3年秋に、「下根子を訪ねた」としています。森氏が高瀬露に羅須地人協会への途上で会った年月は森氏の個人的な体験なので記憶違いも仕方がありませんが、「ふれあい」では大正14年夏に羅須地人協会が設立されその年の秋に訪問したと記してあります。
しかしご承知の通り羅須地人協会の設立年は大正15年です。大正14年秋は賢治はまだ花巻農学校で教鞭をとっていた時期なのです。
ただ、これもまた単なる「記憶違い」と言えるかも知れません。それでも「三人の女性」が「宮沢賢治の肖像」に収録された昭和49年、そして「ふれあい」が連載された昭和55年から60年なら、賢治に関する年譜も資料も充実しているはずです。賢治の親族に確認を取るという手もあったでしょう。
いずれにしても羅須地人協会の設立年や賢治が病を得て自宅に戻った時期など調べればすぐに分かったはずです。
森氏は賢治と親しい間柄だったというのに、評伝を書こうというのに、何故こんな大事な年を二度も誤記したのでしょうか。
「三人の女性」で述べられている昭和3年当時高瀬露は27歳であり、「ふれあい」で述べられている大正14年当時高瀬露は24歳でした。
「三人の女性」で昭和3年についての指摘を受け、高瀬露を「二十二三才の女の人」と書いた辻褄合わせの為に「ふれあい」では羅須地人協会の設立年を「大正14年」としたのでしょうか。
しかし高瀬露の年齢の辻褄は合わせることが出来ましたが、羅須地人協会の設立年という面で結果的に誤記という結果になりました。
二つ目の相違点は、高瀬露が着ていたという着物のことについて。
「三人の女性」では「派手ではなかったが、上品な柄の着物」としているのに対し、「ふれあい」では「もみじ色の、はでではあるが高雅な気分のある和服姿」としています。
なぜここでも記述を変えているのでしょうか。
記憶が曖昧であるなら、先発である「三人の女性」の記述通りにしておくか、着物の柄のことには触れなければ良かったのです。
しかし記憶が曖昧であったにしても両者の印象はあまりにも違い過ぎます。森氏の、高瀬露をいかに悪女に仕立て上げようかという考えが着物の柄の記述の相違点として出てしまったのではないでしょうか。(一般的に悪女は派手な装いをしているイメージがありますから)
(なお、上田哲氏の論文「「宮澤賢治論」の再検証(二)<悪女>にされた高瀬露」において、「高瀬露は、地味で控目な人だったのでいつの年代でも年令より数年ふけて見えたというのが彼女を知る人の共通の印象だった」とあります。異性に会うからといえど、そういうタイプの人がそのような派手な着物を着るとは考えられません。)
森氏が羅須地人協会を設立し下根子に住む賢治の元を訪れたことも、その時賢治を訪問したあとの帰路につく高瀬露とすれ違ったことも否定はしません。(ただ断言はできませんが、「女臭くて……」云々という賢治の言動は森氏の虚構という可能性が考えられます。)
しかしこのたった二つの相違点だけで、森氏のこの話は格段に信憑性が薄れると思います。
![「猫の事務所」調査書[ファイル0508]](https://ntcj-chousa.com/file0508/wp-content/uploads/2025/05/file0508logo.png)