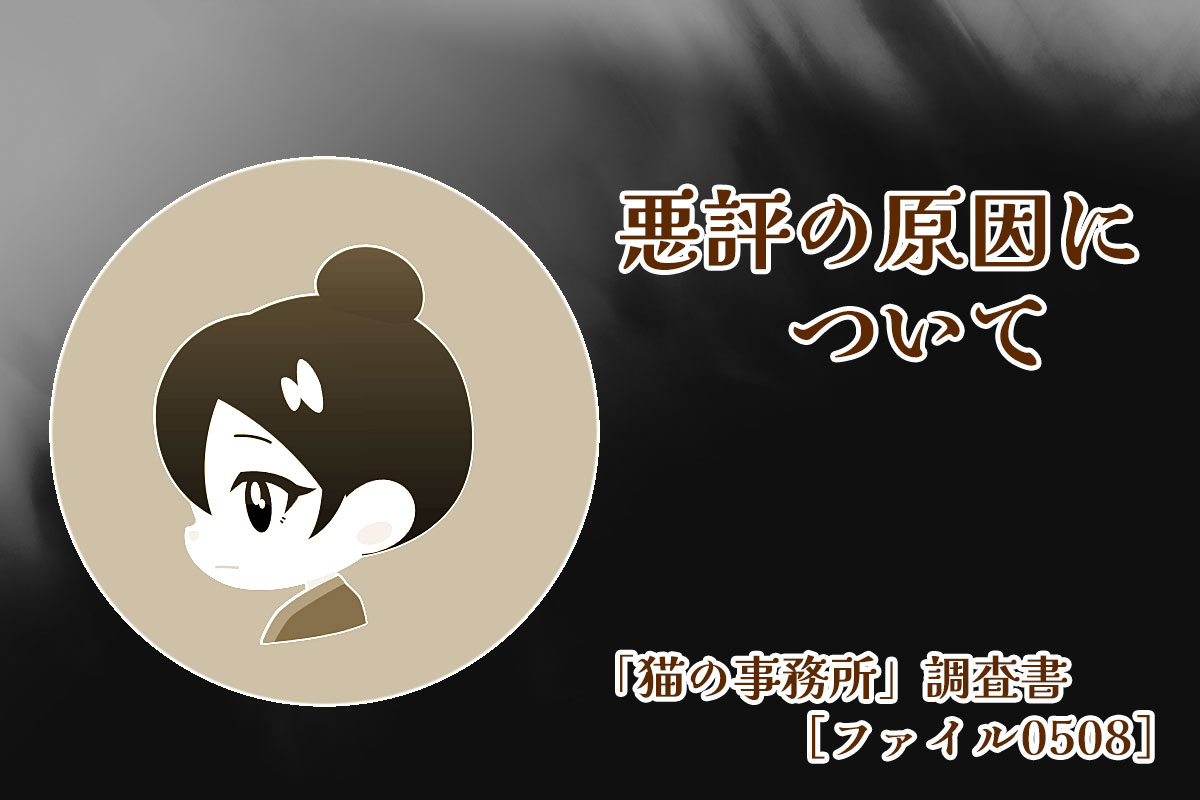悪評の出方・伝わり方
このカテゴリの最初のエントリでも引用した上田哲氏の論文をもう一度ここに引用します。それを元に悪評の出方・流れ方について考えたいと思います。
そのこと(引用者注・高瀬露の愚行やそれに対する賢治の行動などに数々の疑問点や矛盾点が出てくること)を古くからの賢治研究家である鏑慎二郎に話したところ、わたしもあなたと同じような疑問をもっていました。どうもこの話は作り話臭いところがあります。火のないところに煙は立たないから全部否定はしませんがといって次のようなことを語ってくれた。
昔、田舎は娯楽が乏しかったので男と女の間のことについての噂話は大きな娯楽でした。それほどのことでない話も村中をまわりまわっているうちに拡大され野卑な尾鰭背鰭がいくつもついてバトンタッチ毎に変形されるから元は一つの話でもあきられず村中を何回もまわることがあります。高瀬露が賢治のところをしばしば訪ねていたとしたら、こういう噂話の好きな人々の間では恰好の材料だっただろう。
(中略)
ただ、田舎におけるこの種の話は直接的でいくら尾鰭がついても基本的には、単純な構成であるのに賢治と露の話はストリー性があるんです。それから田舎のこういう噂話は大体、村や部落の範囲をめぐっているだけなのに賢治と露の話の場合は、間を飛んで町の方しかも賢治にかかわりをもつ人々の住む町に伝わっているんです。この噂話は、田舎の人が作ったのではなく……あるいは田舎の人でも都会生活の経験者が作ったのかも知れない。また、伝わり方も誰かあやつっている人がいるような気もする。
このような内容であった。現代的にいえば何者かがシナリオを作り、意図的な情報操作が行なわれていたようだという指摘である。
(上田哲「七尾論叢11号」所収「「宮澤賢治論」の再検証(二)―<悪女>にされた高瀬露―」より)
1930(昭和5)年、関登久也氏の母親は訪ねて来た高瀬露の姿を見て怒り、関氏も「女といふのははかなきもの也」と高瀬露を蔑んだような言葉を日記に記しています。(◆)
この時点で既に関氏とその母親は高瀬露の悪評を信じ込んでしまっていました。つまり、それ以前から高瀬露の悪評を聞いていたということになります。
しかし賢治に関わりを持つ人々の住む町に伝わったのは「単純な構成に単純な尾ひれがついただけの話」であり、ストーリー性のある尾ひれが付いたのはそれからずっと後のことと考えるべきでしょう。
前に述べたように人は悪い噂をすぐ信じてしまうものですから、「毎日賢治の元に通いつめた・夜遅くまで居座ることもあった・女房気取りでライスカレーを作った」などという単純な構成に単純な尾ひれの付いた話だけでも充分です。関登久也氏が著書で語っていることもよく読んでみれば「単純な構成に単純な尾ひれがついた程度の話」なのです。
ストーリー性のある尾ひれを作ったのは都会出身者か都会生活を経験した地方出身者ということですが、それに当てはまるのは1926(大正15)年に東京外国語学校ロシア語科に入学しやがて中退、1928(昭和3)年岩手日報社に入社したという森荘已池氏のみです。森氏の東京生活はおよそ1〜2年ほど。著書の時系列的に考えても森氏があてはまります。
それとも他に、「賢治と高瀬露の話を聞いたことのある都会者・都会生活経験者」が陰に潜んでいたのかもしれません。
儀府成一氏はプロフィールに都会生活をしたという記述が見当たりませんし、これまでの悪評を聞いたままに書いたという印象がありますので除外すべきでしょう。
では、その話はどのようにして町まで伝わって行ったのでしょうか。
羅須地人協会の周りに住む農民たちもそれなりに賢治と高瀬露の噂話をしていたとは思いますが、鏑慎二郎氏が指摘するところによると、羅須地人協会の周辺から間を飛んで町の方へと伝わっているということです。該当するのは、「羅須地人協会と町を何度も行き来する人」ということになります。
ここでも真っ先に頭に浮かぶのは高橋慶吾氏ですが、鏑氏の話によれば高橋氏はその人柄からあまり知人から信用されていなかったとのこと、また前エントリで頂いたコメントによると高橋氏は賢治の弟宮沢清六氏にも信用されていなかったことが伺えます。
(コメントを下さいました三島様には厚くお礼申し上げます。)
それならば関登久也氏も高橋氏をあまり信用はしていなかったのではないでしょうか。
そんな人がこんな話をすれば、今風に言えば「スルー」されて消えて行ってしまうはずです。なのに残ってしまい、関氏は高瀬露を「はかなきもの」として実際に辛く当たっています。
それはなぜなのでしょうか。考えられるのは以下の点です。
- 関登久也氏が羅須地人協会を訪ねた際にその噂話(高橋氏ではなく地元の農民たちが話している)を耳にし、高瀬露の姿も目にした
- 高橋慶吾氏→高橋氏をあまり知らず、関家や宮沢家から信用されている誰か→関家と宮沢家
![「猫の事務所」調査書[ファイル0508]](https://ntcj-chousa.com/file0508/wp-content/uploads/2025/05/file0508logo.png)