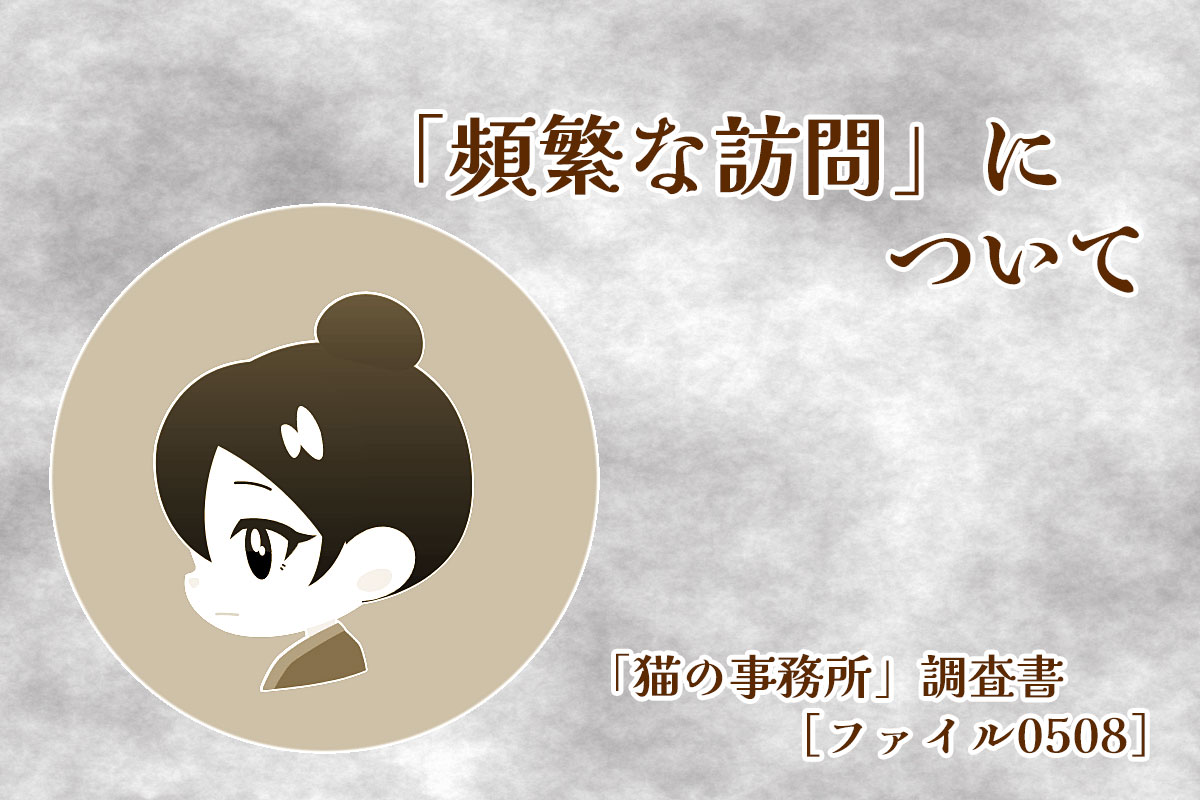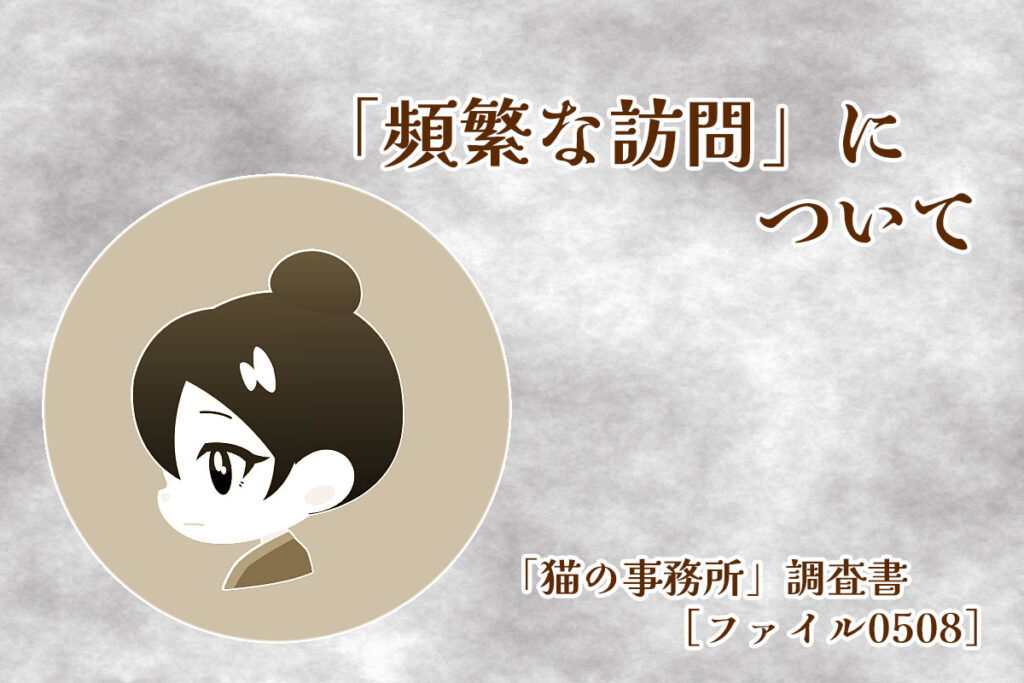
高瀬露を語る上でのキーワードのひとつとなっている、「頻繁な訪問」。ここではそれについて考えていきたいと思います。
まずはそれに関するテキストを悪評系と擁護系からそれぞれ引用していきます。(下線は引用者によるものです)
(略)
その協会員のひとりが、花巻の西方の村で小学校教員をしている女の人を連れて来て宮沢賢治に紹介した。その女の人は村へ稲作指導にきた賢治を彼女の勤めている学校で、はじめて見たのであった。そののち彼女はときどき賢治を下根子の家に訪問するようになった。
(略)
どうやら彼女の思慕と恋情とは焔のように燃えつのって、そのため彼女はつい朝早く賢治がまだ起床しない時間に訪ねてきたり、一日に二回も三回も遠いところをやってきたりするようになった。
(森荘已池「宮沢賢治の肖像」より)
(略)
本を返すという名目で、賢治がまだ床の中で横になっている早朝に、遠いところからやって来たり、日によっては、一日に二度も三度も顔を出すようになってきた。むろん、夜分もそうだった。
(儀府成一「宮沢賢治 ●その愛と性」より)
遠いところをやってきたと森は、書いている。森は、引用文の初めの方で<花巻の西の方の村で小学校教員をしている女の人>と書いている。西の方の村というのは、一九五四年(昭和29)四月一日の市制施行にともなって花巻町ほか湯本、矢沢、宮野目、太田の各村と合併するまでは湯口村といっていた地域であろう。村の小学校というのは、寳閑尋常小学校であった。当時の所在地名は湯口村字鍋倉で一八八九年(明治22)の市町村制施行以前は鍋倉村という小さな村であった。現在の花巻南インターの附近、熊堂の古墳群の辺りと聞いているが、学校は廃校になって跡形はない。
森は、遠いところと彼女が学校の附近に住んでいたように想定しているが、湯口村の何処に住んでいたかによって違うが花巻駅までは四キロから五キロ、賢治が住んでいた羅須地人協会までは五キロ以上六キロは離れているので、何もしないで交通機関のない当時往復するだけで二時間前後はかかるのである。掃除や朝の支度などのためにやって来るのでなければ意味がない。そうだとすると三時間はかかる。無職の人ならよいが、八時ごろには学校に出勤していなければならない。もっとも日曜や休日なら出来ないこともないが、それでも大変なことである。それはよいとして、一日に二回も三回も遠いところをやってきたりするようになった。といっているが、そういうことの出来るような距離ではないのである。
(中略)
向小路二十七番地の実家から通学していたのである。向小路なら羅須地人協会まで一〇分以内でいける。片道の約六キロが省けるから朝早く訪ね一仕事して通勤することも不可能ではない。勤めを持つ身で「一日に二回も三回も遠いところからやって」くることは、出来ない。彼女が、夜の訪問を賢治にたしなめられたと高橋慶吾宛の手紙に書いているが、これは勤めを持つ身で昼間の訪問が出来なかったことを示している。(上田哲「七尾論叢11号」所収「「宮澤賢治論」の再検証(二)<悪女>にされた高瀬露」より)
頂いたコメント・管理人の返信
Unknown(ポラン) 2007年3月20日
はじめまして。
私は愛知県に住む賢治ファンです。
時々このサイトをのぞかせてもらっています。
私も最初の頃は、本に書かれていることを鵜呑みにしていましたが、あるときから次第に「?」がだんだん大きくなっていきました。
このサイトを見つけたとき、ほんとうにびっくりして、それからうれしくなりました。
投稿を再開されたとのこと。
ぼちぼちでもいいので、研究を重ねていってくださいね。
陰ながら応援しています。
ありがとうございました(tsumekusa) 2007年3月21日
ポランさん、初めまして。
コメントありがとうございました。
この問題に疑問を持っている方と知り合えて、
本当に嬉しいです。
度々お越し下さっていたのに一年近くも
放置状態にしてしまい申し訳ありません。
出来る限り頑張って行こうと思いますので
これからもよろしくお願い致します。
![「猫の事務所」調査書[ファイル0508]](https://ntcj-chousa.com/file0508/wp-content/uploads/2025/05/file0508logo.png)