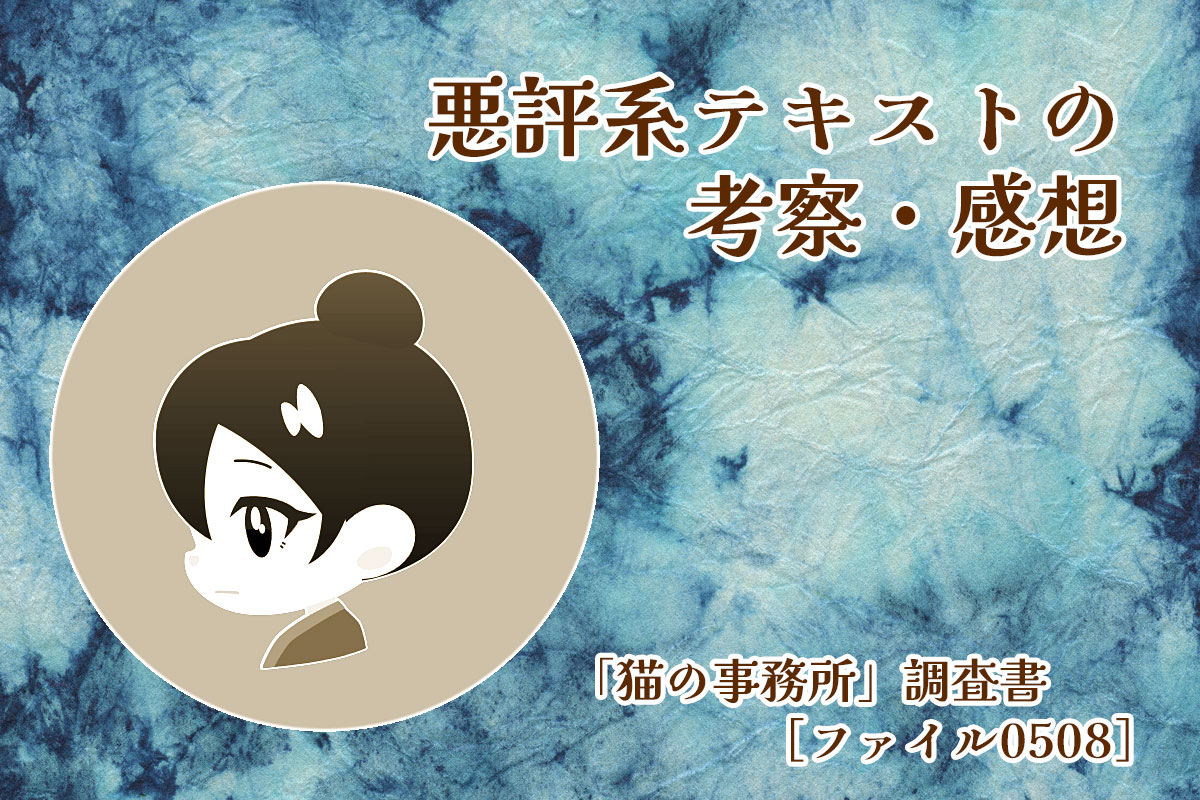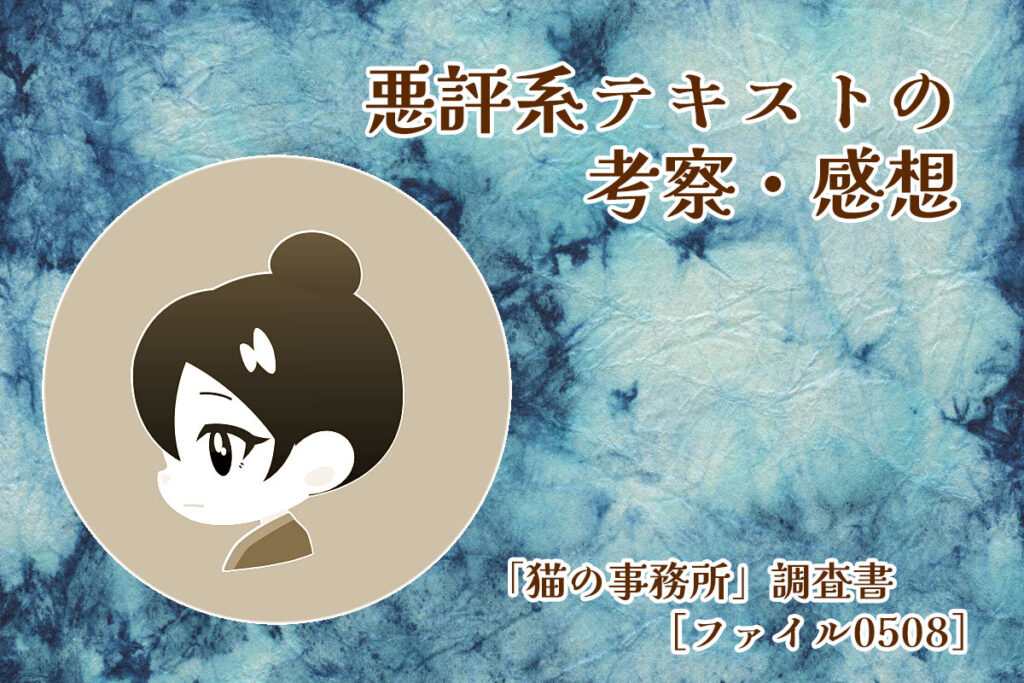
高瀬露の悪評の出所は別にありますが、それを全国的に広めることとなったのは森荘已池氏の「宮沢賢治と三人の女性」(以下、「三人の女性」)でしょう。
まずは、同書から高瀬露に関する記述を引用していきます。
(居留守事件、ライスカレー事件、レプラ発言、中傷の件を除きます。その件については後日考察させて頂きます)
一九二八年の秋の日、私は下根子を訪ねたのであった。
(中略)
ふと向こうから人のくる気配だった。私がそれと気づいたときは、そのひとは、もはや三四間向うにきていた。(湿った道と、そのひとのはいているフェルトの草履が音をたてなかったのだ。)私は目を真直ぐにあげて、そのひとを見た。二十二三才の女の人で和服だった。派手ではなかったが、上品な柄の着物だった。私はその顔を見て異常だと直感した。目がきらきらと輝いていた。そして丸顔の両頬がかっかっと燃えるように赤かった。全部の顔いろが小麦いろゆえ、燃える頬はりんごのように健康な色だった。かなりの精神の昂奮でないと、ひとはこんなにからだ全体で上気するものではなかった。歓喜とか、そういう単純なものを超えて、からだの中で焔が燃えさかっているような感じだった。私はそれまで、この女の人についての知識はひとかけらも持ち合わせていなかった。――が、宮沢さんのところを訪ねて帰ってきたんだなと直感した。私は半身、斜にかまえたような恰好で通り過ぎた。私はしばらく振り返って見ていたが、彼女は振り返らなかった。
次に、森氏が昭和55年から60年まで朝日新聞岩手版に連載していた「ふれあいの人々 宮沢賢治」(以下、「ふれあい」)というコラムにもこの話の記述がありますが、「三人の女性」とは異なる部分が少々見られるのでそちらも引用し、両者を比較したいと思います。
それは、紅葉がほんとうに美しい、この秋一番という好天の日だった。何軒か、老杉と紅葉する大樹の混こう林の中に、大きな農家が何軒かあった。羅須地人協会が旧盆に開かれたその年の秋の一日であった。そこへ行くみちで、私はひとりの若い美しい女の人に会った。その人は、そのころからはやり出した、もみじ色の、はでではあるが高雅な気分のある和服姿であった。その着物と同じように、ぱっと上気した顔いろに、私はびっくりした。少し前まで興奮した「時間」があったのだなと私は思った。
大正十四年夏、この協会ができた時、お訪ねしたいと手紙を出すと、今はとても忙しいから、秋においでなさいと返事があった。駄(だ)客、閑客の類だから、ヒマになったらおいで、ということだと、素直に受け取った。きょうが初めての未知の家への途上で、ばったりと、この女人に会ったのである。
(中略)
この女の人が、ずっと後年結婚して、何人もの子持ちになってから会って、色々の話を聞き、本に書いた。この人の娘さんが、亡き母の知人に「古い日記に母が『宮沢賢治は、私の愛人』と書いております」と話したという。これを耳にして、古い記憶にあざやかな、若い時のこの女人の顔と、中年もすぎ、生活とたたかい、りっぱに子を育てた年輪のある顔とが、どうしても重ね合わせられなかったことを思い出していた。
両者を読み比べてみると、相違点が二つあることに気がつくと思います。
次エントリにてそれを考察して行こうと思います。
![「猫の事務所」調査書[ファイル0508]](https://ntcj-chousa.com/file0508/wp-content/uploads/2025/05/file0508logo.png)