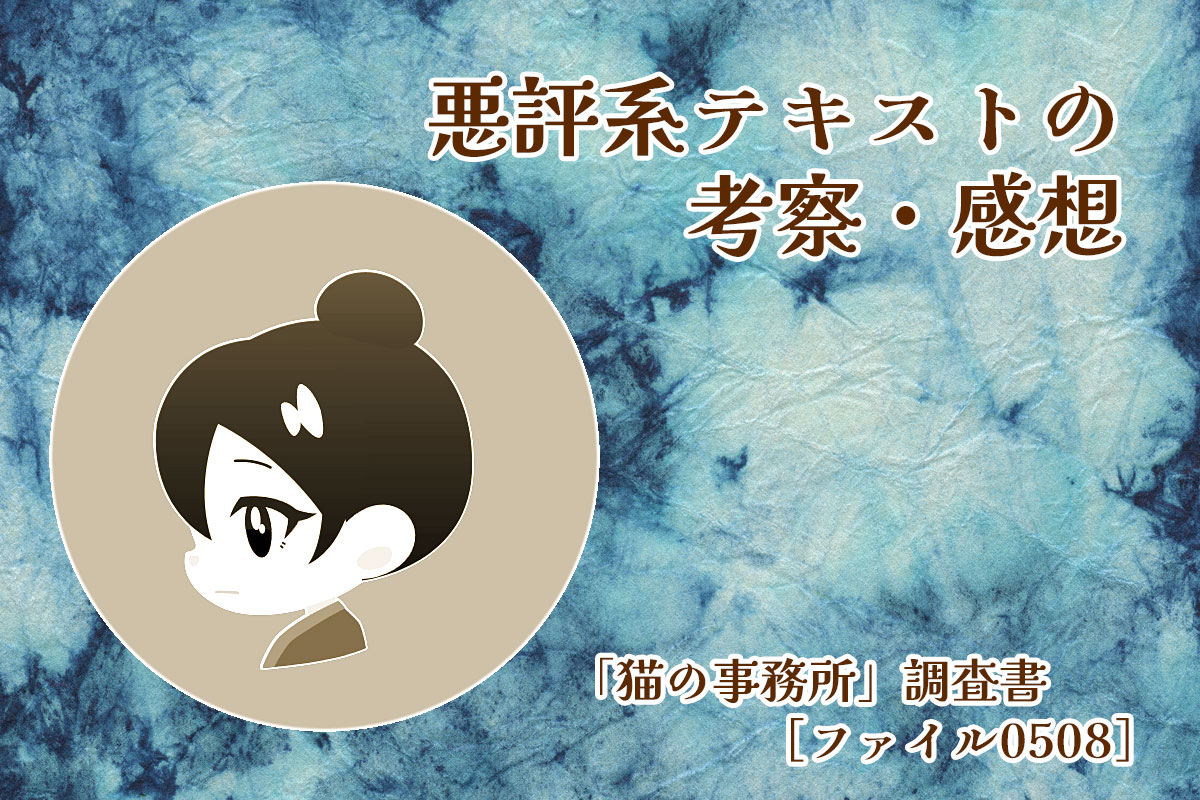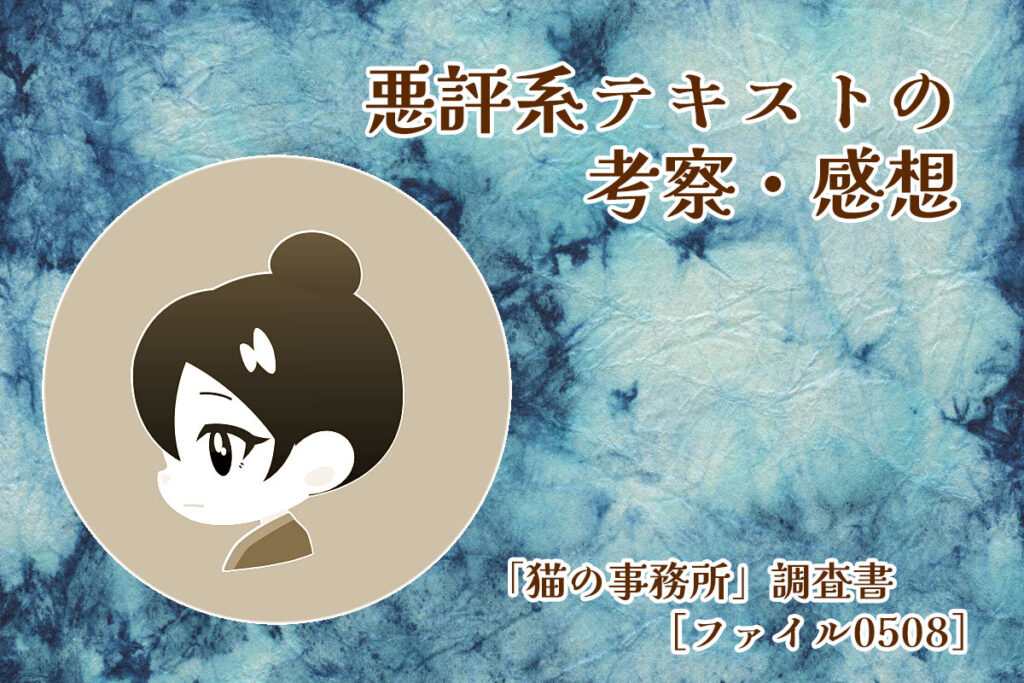
当エントリでは、森荘已池氏の高瀬露に関する記述を読み個人的に引っ掛かった部分への意見や森氏の記述に対する感想などを述べたいと思います。
まず、すれ違う際の高瀬露の様子の描写について。
「三人の女性」では随分と細かい描写をしていますが、普通道ですれ違った人の細かい様子など記憶に無いものです。そこまで詳しく覚えているなら相手を凝視する必要があります。
しかしそちらの方が異常だし、相手にも失礼です。
ただこの時高瀬露は和服を着ていて草履を履いていたゆえに歩行速度が遅めであったから、詳しい観察が出来たとも言えるかも知れません。
しかし、「目がきらきらと輝いていた。そして丸顔の両頬がかっかっと燃えるように赤かった。全部の顔いろが小麦いろゆえ、燃える頬はりんごのように健康な色だった。」だけで「異常だと直感」するなど、少し飛躍しすぎではないでしょうか。
「かなりの精神の昂奮でないと、ひとはこんなにからだ全体で上気するものではなかった。歓喜とか、そういう単純なものを超えて、からだの中で焔が燃えさかっているような感じだった。」これもまた考えすぎではないでしょうか。
「ふれあい」ではシンプルにすれ違った際目に入ったままを記し、「三人の女性」ほど不自然な点はありません。
しかし、「ぱっと上気した顔いろ」をしていただけで「少し前まで興奮した「時間」があったのだな」という、やはり飛躍し過ぎという感じがする一文も含まれています。思いを寄せる(とされる)相手に会ったのであるなら、目を輝かせたり顔を赤らめたりするのはごく自然なことなのではありませんか。
そして次に、「ふれあい」の最後の記述。これには私はとても憤りを覚えています。
「この女の人が、ずっと後年結婚して、何人もの子持ちになってから会って、色々の話を聞き」とありますが、森氏が高瀬露と会ったのは後にも先にも羅須地人協会の途上での一回だけです。
森氏は上田哲氏にも直接それを語り、上田氏は「再検証(二)」にそのことを以下のように記述しています。
森は彼女に逢ったのは、<一九二八年の秋の日><下根子を訪ねた>(注 下根子とは、賢治の羅須地人協会である)その時、彼女と一度あったのが初めの最後であった。その後一度もあっていないことは直接わたしは、同氏から聞いている。
高瀬露の娘が語ったという話も本文を良く読めば人づて、つまり高瀬露の知人とされる人物から更に第三者を介して聞いたとされる話のようです。
いわゆる「友人の友人の話」のようにぼやけていてかなり信憑性は薄いものなのです。(女性週刊誌の芸能記事に良くある手口です)森氏の完全な虚構である可能性も考えられます。
高瀬露が賢治のことを本当に日記に書いていたとしても、
- 実はただ単に「敬愛する宮沢賢治先生」という内容だったのが、伝言ゲームの要領で伝えられて行くうちに言葉が変わってしまい、森氏のところに届く時には「宮沢賢治は、私の愛人」となってしまっていた
- または森氏に届いた「高瀬露の日記の記述」は別の意味だったが、高瀬露に対する固定観念を持つ森氏がその言葉を歪めて取ってしまった
という可能性もあります。
森氏は、何故こんな必死になってまで高瀬露=悪女像を定着させようとしたのでしょうか。
私には知る由もありませんが、どんな理由があるにせよやはりきちんと調査をしてから記述をすべきだったのではないでしょうか。
ご自分の書かれる文章は娯楽小説でもゴシップ記事でもないことは自覚されていたのでしょうか。名前を伏せてさえいれば、好き勝手に書いても構わないなどとお考えだったのでしょうか。
きちんとした調査を怠ったどころか記述を二転三転させ、あまつさえすぐに分かってしまう嘘までついた。このような「やってはいけないこと」までして高瀬露を悪女に仕立て上げようとした森氏のやり方は、はっきり言ってあまりにも醜いと思います。
![「猫の事務所」調査書[ファイル0508]](https://ntcj-chousa.com/file0508/wp-content/uploads/2025/05/file0508logo.png)