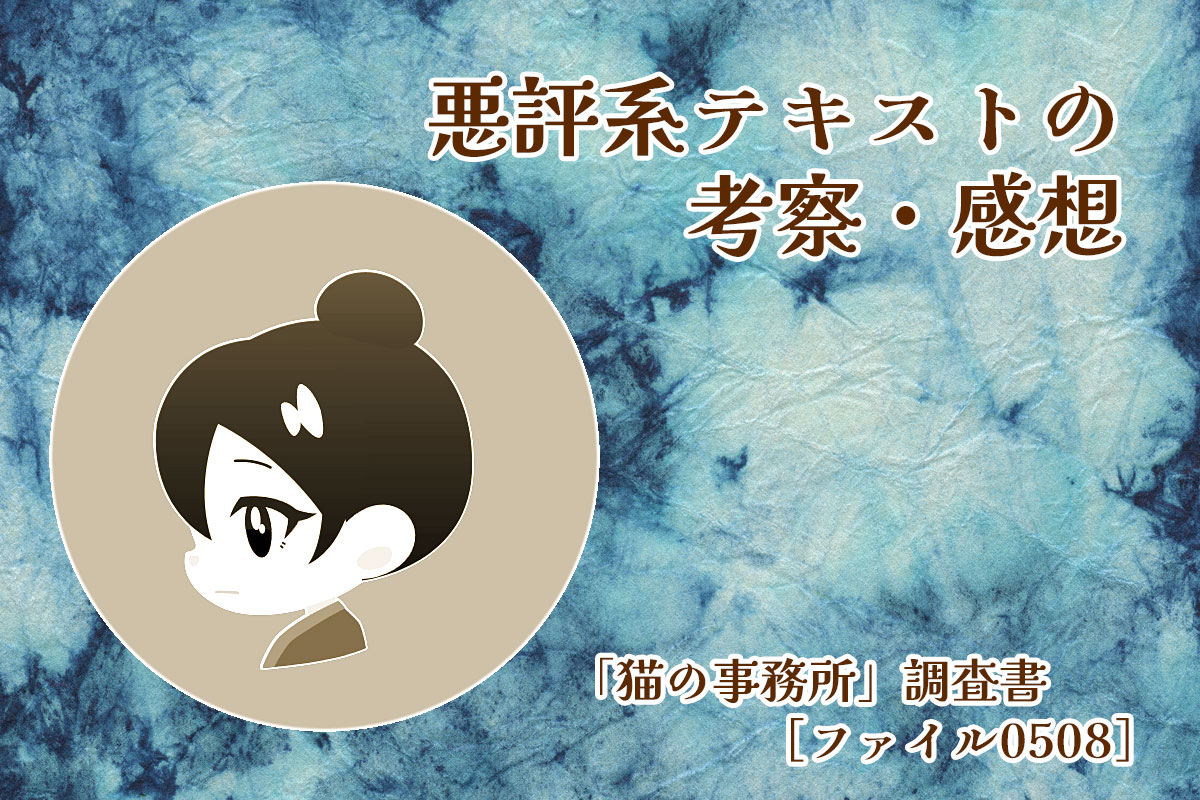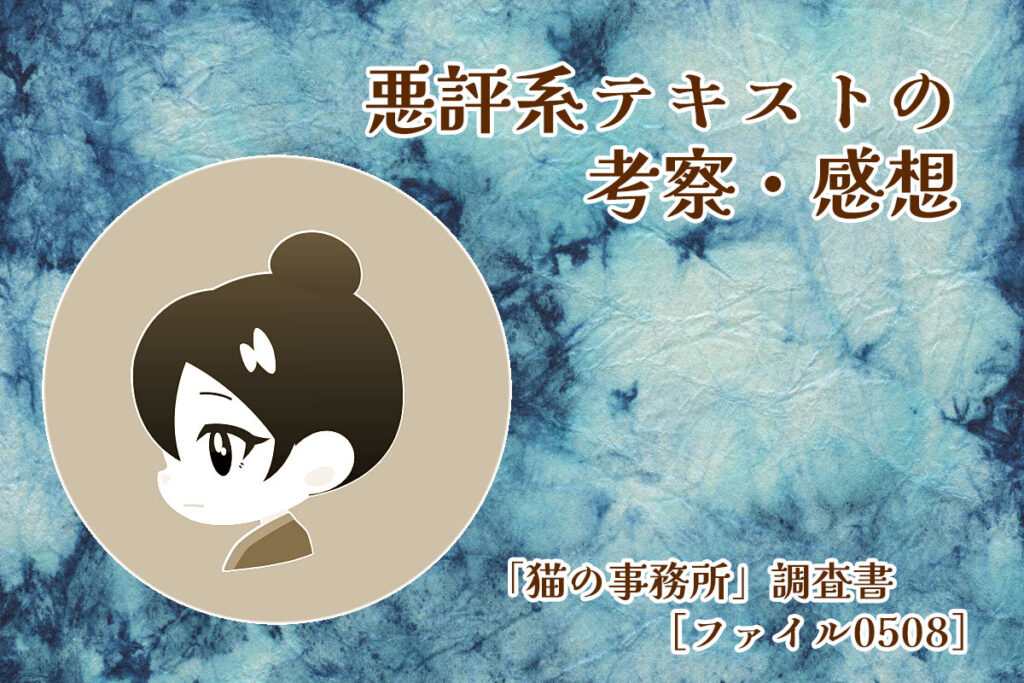
なお、儀府氏は高瀬露に関する記述の最後にこのようなことを記しています。
一つは、賢治が内村康江をそう思ったり呼んだりしたのはいいとして、われわれまでそれに做って、この人のことを悪魔のように見たり云ったりするのはやめたい、ということだ。突然こんな風に書くと、一般の読者は「何を書いているのだろう」と思ったり、「その女の人は、そんな風に見られたり、書かれたりしている人なのか」と、疑問を抱かれると思う。これは、この人のことは誰もほとんど語らず、書かなかったこと――万一書いても、ほんの何行かでサラリと片づけていたことから生じる疑問にすぎない。
理由は、彼女が平凡な家庭の主婦(それは大へん倖せなことなのだが)で、別に知名度の高い人でもなかったのと、何より、宮沢家に対する遠慮からだったと思われる。むろん宮沢家としても、内村家としても、二人のことはあまりふれたくない、ふれてもらいたくない事柄かもしれない。その気持はわかるけれど、これ以上いつまでもウヤムヤにしておかないで、この辺で事件の真相とまではいかなくても、ある程度まともな、公平な、と思われる一応の見方だけでもしておくべきだと思って、私は貧しい自分の仕事のなかに、この「やさしい悪魔」の章を加えることにしたのである。
(中略)
書いておきたいことの二つ目は、実はこの人についてである。あの”運命のカレーライス”事件を境にして、二人の間は画然と割れたあと、賢治に対するいろんないやがらせをしたというが、どのようなものだったのだろうか。「像に釘うつ」と賢治が書いているのをみても、非情に情熱的だったと云われる人柄からおして、かなり思い切ったことをしたのではないかとも思われる。
今、それに当たっている時間は私にはない。目をつぶって追想の過程としてつづけていえば、いろんなことが嫌になるくらいたとえあったとしても、とにかく内村康江は、宮沢賢治に求愛し、求婚した、最初の女性であったという事実、同時に、この人ほど熱烈に賢治に想いを寄せ、その懐にまっしぐらにとび込もうとした人はいなかった、という点で、その名を何かに録しておきたい人だと思うのだ。
凶作、冷害、不作がくり返される東北の暗鬱な自然と、どこに明るさをもとめたらよいのか分からない不況下の農村を背景に、田園にユートピアの建設をゆめみ、独居してみずからも鍬をふっている宮沢賢治に、人間の理想像をみたとばかり、ピタリと照準をあてたイーハトーヴォの一人の若い女性に、私はとにかく拍手をおくりたい。
再び失礼なことを言ってしまいますが、「開いた口が塞がらない」というのが正直な感想です。
本当に高瀬露(内村康江)のことを「悪魔のように見たり云ったりするのはやめたい」「拍手をおくりたい」と思い、「ある程度まともな、公平な、と思われる一応の見方だけでもしておくべきだ」と思ったのであるなら、なぜその件についての検証を怠り、森荘已池氏の文章に更に尾ひれを付けるようなことをしたのでしょうか。
儀府氏も研究者として人間として「やってはいけないこと」をやってしまったのです。
儀府氏は高瀬露を評価し庇うような発言をしていますが、結局のところ(一応)やめにしたいはずの「悪魔のように見たり云ったり」する行いを助長し、また「まとも」で「公平な」見方など全くしていないのです。
「相手のCは、自分のように働いて食べるのが精いっぱいだという職業婦人ではなくて、名も富も兼ねそなえた恵まれた美しい女性であるということがシャクだった。」
この一文に、儀府氏の本音が凝縮されているような気がします。儀府氏が高瀬露に対して抱く歪んだ理想像が見えるような気がします。
そして悲しいことに、この尾ひれだらけの「フィクション」が史実として長年流布することになってしまいました。
最後に、私の心に引っかかる一文を引用します。
「賢治に対するいろんないやがらせをしたというが、どのようなものだったのだろうか。」
「高瀬露の中傷行為伝説」を検証するヒントとなる一文だと思います。それについては後日考察します。
![「猫の事務所」調査書[ファイル0508]](https://ntcj-chousa.com/file0508/wp-content/uploads/2025/05/file0508logo.png)