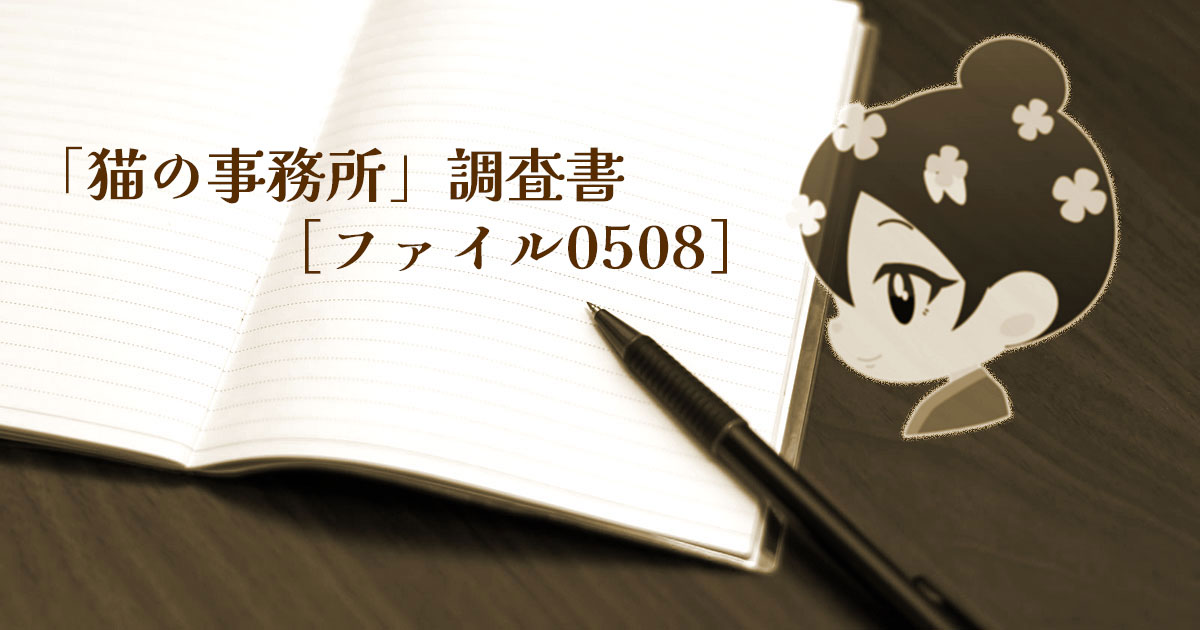上田哲氏の論文「「宮澤賢治伝」の再検証(二)ー<悪女>にされた高瀬露ー」より、周囲の人々の高瀬(小笠原)露への印象・評価について記されている部分を引用しています。
彼女との交流は、晩年近くになってからであるが、露の二人の娘とは小学校時代からの幼友達で比較的古くから露を知っていたE.Kという人がいる。遠野在住の歌人であるが尾上紫舟賞の受賞者で日本歌人クラブの理事でもある。
(中略)
高瀬露と賢治についての伝説は私が話すまで知らなかったが、露が賢治を度々訪問していたことは、彼から聞いていた。それで露と賢治についていろいろ聞いてみた。彼の証言を次に紹介する。「露さんは、「賢治先生をはじめて訪ねたのは、大正十五年の秋頃で昭和二年の夏まで色々お教えを頂きました。その後は、先生のお仕事の妨げになっては、と遠慮するようにしました。」と彼女自身から聞きました。露さんは賢治の名を出すときは必ず先生と敬称を付け、敬愛の心が顔に表れているのが感じられた」
(注・高瀬露は、賢治のところへ訪問したのは昭和二年(一九二七年)夏頃までといっているが、森荘已池は『宮沢賢治と三人の女性』の中で(七四ページ〜七五ページ)<一九二八年の秋の日>羅須地人協会の賢治宅を訪ねる途中の道で彼女にあっていると書いている。併し、その年の八月十日発熱し豊沢町の実家で病床に伏せていたのである。(<校本全集十三巻書簡番号二四三号九月二十三日付沢里武治宛参照>))さらにK氏は高瀬露の人柄については次のように語っている。
「露さんを小学校の友だちの母親として知っていたが、親しくなったのは十代の終わりの頃。結核で入院していたわたしを多忙な主婦と教員の生活を割いて度々見舞に来てくれた。自分が娘の幼友達だったということからではなく病人、老人、悩みをもつものを訪問し力づけ、扶けることがキリスト者の使命と思っていたのである。彼女は私だけでなく多くの人々に暖かい手を差し伸べていることがいっとはなしに判り感動した。わたしも彼女に大分遅れて同じカトリック信者になったが、昔の信者の中には、露さんのような信者をよく見かけたが、今の教会にはいない。露さんは、「右の手の為す所左の手之を知るべからず」というキリストの言葉を心に深く体していたような地味で控えめな人だった。また、世話ずきで優しい人で見舞の時枕頭台やベッドの廻りの片付けなどをしてくれた。それとともに誇り高く自分を律するのに厳しい人で、不正やいい加減が大嫌いだが、他人の悪口や批判を決して口にしなかった。ただ、後輩や若い人には、先輩としての義務観から忠告や注意をして誤解されるようなこともあったようだ。」
(中略)
また、彼女の二度目の青笹小学校勤務時代の同僚でS.K氏という人がいる。大正十五年生まれであるというから六十九歳。馬が趣味の元気な人であり、小笠原露について鮮明な記憶をもっている。彼はまだ三十代の若さで教務主任をしていた。現在は退職して花巻市のY町に住まっている。S.Kの青笹小学校赴任は一九五七年(昭和32)で小笠原露の退職は一九六〇年(昭和35)だったから三年間一緒に勤務していたのである。S.K氏は露について次のように語っている。
「小笠原先生は、当時養護教諭として勤務しており、児童の健康管理と保健の授業をしていました。仕事ぶりは真面目で熱心な方でした。良く気のつく世話好きな人だったので児童からもしたわれていました。それから人ざわりの良い、物腰の丁寧な人で、意見が違っても逆わない方だったので同僚や上司、父兄、周囲の人々に好感を持たれていました。普段は目立たない人でしたが、興に乗るとよく話をしました。」
そして露と賢治のことについては「はっきり憶えていませんが、なにかの機会に、若い頃から宮沢賢治先生を敬愛し、おたずねしていろいろとお教えを受けた、と話されたことがあります。」と語ってくれた。次に筆者自身の小笠原露(高瀬露)の印象とわたしが高瀬露と賢治とのかかわりの問題についてなぜこのように追求するようになったかの経緯についても少しふれて見よう。わたしが初めて高瀬露にあったのは、一九五三年(昭和28年)十月二十六日盛岡のお城下の岩手教育会館で開かれた「佐藤佐太郎氏歓迎歌会」の席上であった。
(中略)
名前が紹介された時、頭を下げた彼女の姿を地味な人と思ったこととどこかで逢ったことがあるという思いが心をよぎったが、その後彼女のことは忘れていた。もちろん彼女が賢治とかかわりのある人などとは全く知らなかった。その翌年の十二月何人かの友人たちと『岩手短歌』という地方歌誌を創刊した。便宜上わたしが発行人となり発行所も盛岡カトリック教会内のわたしの宿舎にした。地方新聞の学芸欄に度々紹介記事が載ったので入会の申込みや問い合わせの手紙が来た。その中に小笠原露の手紙もあった。
(中略)
ところでそれから間もなく小笠原露に逢ったのです。月日は憶えていませんが盛岡市四ツ家町のカトリック教会の日曜日の午前九時からはじまる第二ミサの席である。昨年佐藤佐太郎歓迎歌会で逢った中年の婦人に似た人を見付けた。
(中略)
帰りがけに声をかけたところ遠野教会の信者の小笠原露であることと長女が盛岡の志家町にあるベトレヘム外国宣教会で調理の仕事を担当している同じ宣教会の日本人スタッフとして同僚であることもわかった。小笠原露の印象は、古いキリスト者によくある控えめでなにごとにも自分を抑制しようとするタイプと感じられた。そのうちに岩手のカトリック教会の歴史をまとめる仕事をするようになり、賢治の詩歌作品の中に、一八九七年から一九二二年まで盛岡天主公教会に二十五年間在任、岩手の宣教に大きな足跡を遺しただけでなく地域の文化、福祉にも貢献したアルマン・プジェ神父を詠ったもののあることを知り、賢治の作品を調べていくうちにカトリシズムの投影がかなり感じられ、「近代日本文学とキリスト教」というわたしの研究領域の中の対象に賢治が入って来た。
こういうことで賢治と高瀬露についてのことも調べてみようと関登久也の『宮沢賢治素描』、
高橋慶吾の「賢治先生」(『イーハトーヴォ』創刊号所収)などを読んでびっくりした。森荘已池の『宮沢賢治と三人の女性』は、中々手に入らずすこし遅れて読んだ。人々は、キリスト者や外の宗教者を紹介するとき儀礼的修辞的に「敬虔」ということばをよく使う。ぐうたらで不謹慎な人間の標本のようなわたしまでもカトリックであることが知れると「敬虔なクリスチャンであられる上田先生」などと紹介され苦笑することが折々ある。しかし高瀬露の場合は、敬虔ということば通りの人柄に思われた。そういう彼女を知っているわたしには、流布している高瀬露の話は信じられなかった。それで夏休みの休暇などを利用してまず花巻に行き学校や教会など一般の人々の彼女の印象などを聞き出そうとしたが花巻は、土地を離れて二十年以上経っているので高瀬を知る一般の人々は探せなかった。(中略)
次に遠野に行き調べたがカトリック教会関係は、彼女が健在であるので調査のようなかたちはとれないから世間話の中でそれとなく彼女のことを聞いたところ「熱心な信者さんで親切な方」という異口同音の評価だった。次にわたしが『岩手短歌』の発行人、県歌人クラブの役員だったのと彼女も短歌を作っているので短歌にかこつけて土地の歌人たちをたずね彼女と交流のあった人々からこれもそれとなく聞き出したところ評判がよかった。中には彼女の教え子の親もいた。ただ賢治の教え子で遠野地区の教員を歴任した高橋武治(入婿で改姓—沢里)の周辺と婚家にかかわる人々の間では「悪女」説が信じられ彼女の評判は悪かった。最後に小笠原露のカトリック入信の導き手となったY.Mは、小笠原露を高く評価し模範的信者で、家庭の子供たちに対する宗教教育も適切であり、母親の感化で娘の一人はゲオルグの聖フランシスコ会の修道女になっている、と語っている。Y.Mは露の信仰生活についていろいろ具体的な例をあげて彼女を奨揚しているが省略する。
上田哲 「宮澤賢治伝」の再検証(二)ー<悪女>にされた高瀬露ー 1996(平成8)年
![「猫の事務所」調査書[ファイル0508]](https://ntcj-chousa.com/file0508/wp-content/uploads/2025/05/file0508logo.png)