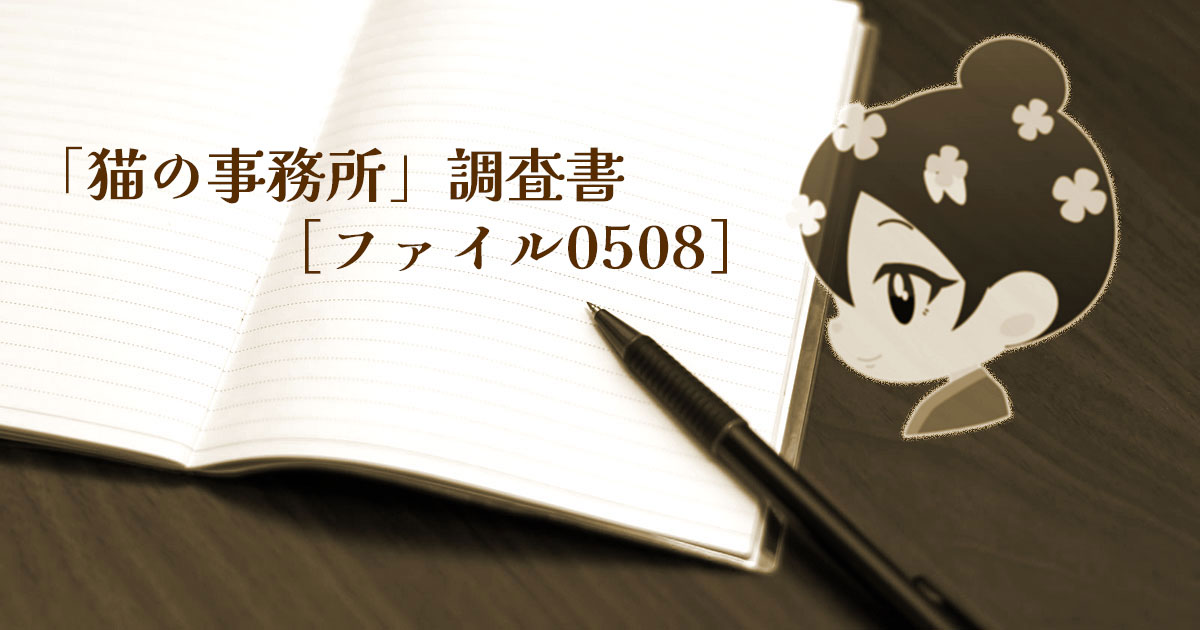河出書房新社「図説 宮沢賢治」92ページから94ページに掲載されている上田哲氏のコラム「賢治をめぐる女性たち——高瀬露を中心に」より、記事に対応した部分を抜粋して引用しております。
中学卒業後岩手病院に入院したときに片思いした氏名が特定できない看護婦、「羅須地人協会」に一時期出入りしていた高瀬露、「三原三部」の伊藤ちゑ、保母をしていたという氏名不詳の女性がこれまで話題にのぼっている。
このうち高瀬露について流布している話は、かなり歪められて伝えられているので再考したい。彼女が夜となく昼となく訪ねて来たのに困った賢治が、自分を癩病だといって顔に灰を塗ったり、「本日不在」のはり紙をして彼女を遠ざけようとした話がある。また、彼女があるとき羅須地人協会でライスカレーをつくっていると、肥料設計の依頼に数人の百姓が来て彼女を見てびっくりしたので、賢治は困って百姓たちにご馳走し、自分は「食べる資格がない」と言ってそのまま二階に上がってしまった。彼女はひどく腹をたてオルガンを乱調子に鳴らしたので賢治が「昼はお百姓さんたちがみんな働いてる時だから止して下さい」といましめたという話がある。
それぞれいくらかのちがいはあるが大筋は同じ内容で、森荘已池をはじめ数人の人びとによって伝えられてきた。しかしこれを書いた人びとはライスカレー事件の現場を見たことも、灰を塗った賢治の顔を見たことも、賢治が自分は癩病だと高瀬に語っているのを聞いたこともないのである。さかのぼっていくと羅須地人協会に出入りしていた高橋慶吾という情報源にたどりつくのである。
これらの話は賢治の生前から高橋慶吾によって花巻の人びとや賢治ファンの間に広く伝えられていた。活字化されたのは一九三九年(昭和十四)十一月発行の『イーハトーヴォ』創刊号掲載の「賢治先生」という文章。十月二十三日に行われた盛岡の宮沢賢治の会の例会での高橋慶吾の談話の要約である。
(中略)
不思議なことに、多くの人は、これらの話をなんらの検証もせず、高瀬側の言い分は聞かず一方的な情報のみを受け入れ、いわば欠席裁判的に彼女を断罪している。
今、ことの真偽を十分考証する紙面がないので、これまで明らかにされていなかった高瀬側からの情報をいくつか紹介するのでこの問題を再考する資としていただきたい。
高瀬露は自分についての悪評を知らなかったわけではない。『イーハトーヴォ』創刊号の高橋慶吾の文章や第十号の関徳弥の文章に、身におぼえのないことが書かれているのを読んでいるのであった。それなのに反論も弁解もしていないのは不思議である。明らかな犯罪者でも否認したり弁解したりするのが普通である。彼女は生涯一言の弁解もしなかった。
この問題について口が重く、事実でないことが語り継がれている、とはっきり言ったほか、多くを語らなかった。これは彼女がキリスト者であったことによるのかもしれない。肉体的苦痛はもちろん、貧窮、迫害、誹謗などを自分の十字架としてにない、キリストの十字架の御苦に合わせ献げるため甘受するといった考え方が昔の信者にはあった。また、どうしてこのようなうわさを流布されるようになったかを話せば傷つく人のあることも考えていたようである。
(中略)
関登久也は「賢治素描(五)」(『イーハトーヴォ』第十号)の中で、賢治が<亡くなられる一年位前>訪ねて来て、<賢治氏知人の女の人が賢治氏を中傷的に言ふので><賢治氏は私に一応の了解を求めに来た>と述べている。
賢治が関を訪問、<知人の女の人>が賢治の中傷をしていることについて誤解されないよう了解を求めたことを否定しないが、賢治は、その女が中傷している現場を見聞したのではなく、賢治を中傷している女がいるという人の話を、信じただけのことである。
関は、あからさまに高瀬露とはいっていないが、多くの人はそう受けとめている。しかし、当時の彼女は、賢治の中傷をして歩くために花巻まで出かけられるような状況ではなかった。
彼女のいた上郷村は、遠野から村二つ隔てた東方八キロの地点にあり、遠野駅までの通常の交通手段は徒歩であった。花巻までは、当時は二時間近くかかった。本数ももちろん少なかった。朝出ても、ちょっと用事が手間どると泊まらなければならなかったと聞いている。
また、そのころ長女を懐妊していて、産休はなく、年休のかわりに賜暇はあったが、文字どおり賜るもので、休みをいただくのは容易ではなかった。こんな状況なので体をいたわり遠出をさけていたという。そして新婚早々の生活に満足していたのである。
上田哲「賢治をめぐる女性たち——高瀬露を中心に」 河出書房新社「図説 宮沢賢治」92〜94P 1996(平成8)年
![「猫の事務所」調査書[ファイル0508]](https://ntcj-chousa.com/file0508/wp-content/uploads/2025/05/file0508logo.png)