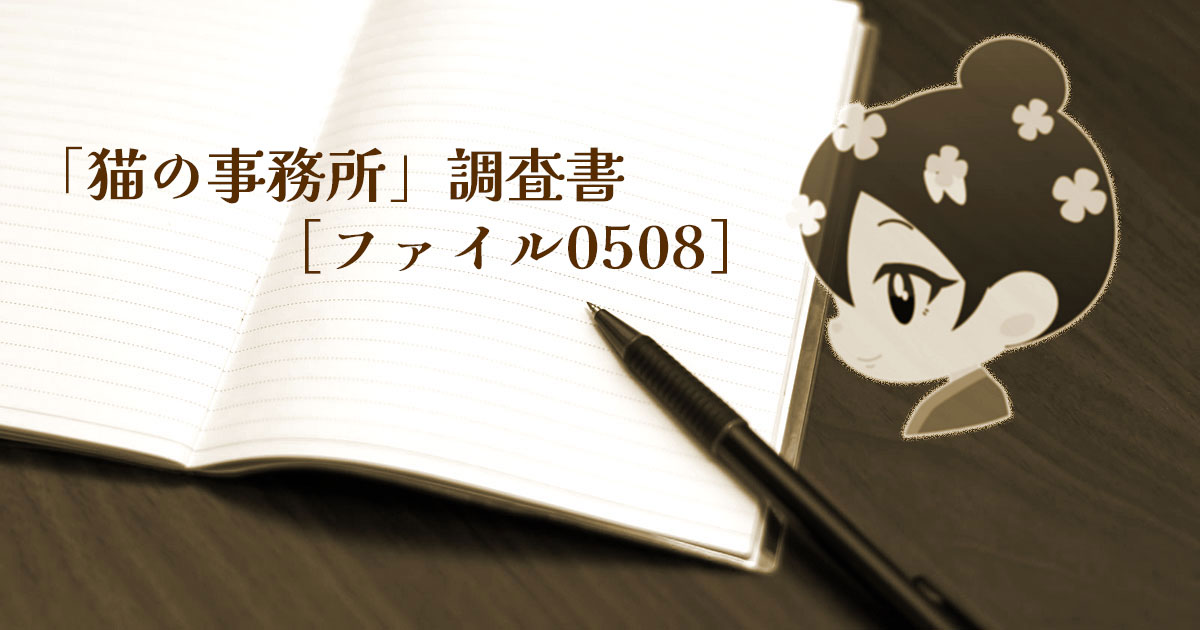上田哲氏の論文「「宮澤賢治伝」の再検証(二)ー<悪女>にされた高瀬露ー」より、花巻におけるキリスト教伝導関連の記述を引用しています。
実は、花巻地方は保守的、世俗的気風の強い土地柄で中々キリスト教が定着しなかった。
花巻に置ける再宣教後のキリスト教徒の動向は一八七八年六月一九日花巻の箱崎ヨウスケ(原文ラテン語・氏名・地名ローマ字)という十九歳の青年が天主公教会のフランス人宣教師プロトランド神父から洗礼を受けた記録が残っている。これが現存する一番古いものである。その頃まだカトリックの教会は花巻にはなく巡回伝道か、箱崎が盛岡に出向いての入信かは不明である。カトリックは一八八七年頃花巻城跡の附近の坂の上に盛岡天主公教会の管理下にある伝道所を花巻城跡附近に置き浅井富人伝道士を派遣していた時期があるが、短い期間で閉鎖したという。
高橋や高瀬の通っていた教派のバプテスト教会は当時浸礼教会といっていた。花巻に一番早く伝道のベースを置いたのはこの教派である。一八八〇年十一月十日講義所が開設されたが一八八五年九月にはこれも閉鎖になった。その後長年この教派の伝道は見られなかった。
次に日本基督教会(—教派—太平洋戦争中の宗教政策によって作らせられた現在の日本キリスト教団とは異なる。)が一八八九年盛岡の日本基督教会から林竹太郎伝道師、三浦徹教師が交互に来花巡回伝道を毎週一回行い翌年六月から内田芳雄伝道師が定住し講義所を開設しブルベッキ博士や島田三郎らの知名人を招いての公開演説会を開き盛んに伝道につとめ十六、七人の信徒を得るようになった。一八九一年頃にデサイブルス派(クリスチャン教会)も花巻に教会をもち福井捨助(号松湖)が牧師として在住していた。北村透谷がこの教派の伝道を扶けるため一八九三年夏この教会に立ち寄っている。この教会も一九〇〇年代にはなくなっている。いずれも教勢の伸展が思わしくなく撤退しているのである。
なお、一八九一年(明治24)〜九三年ごろニコライが佐藤庄五郎家の空家に仮寓し、正教会の伝道所を開設したという、少々日本の近代キリスト教会史を知っている者には噴飯の伝説が郷土史家によって伝えられ、一部の賢治研究書が引用している。
ニコライは一八七〇年には掌院の位で日本宣教の最高責任者となり八〇年には主教(仏教の僧正に当る)に叙聖され、九一年には主教座聖堂である東京復活大聖堂(ニコライ堂)を建てたばかりで忙しく、しかも全日本の正教会を統括する責任者の身で花巻に仮寓し、伝道するなど在り得ない。石川喜三郎『日本正教会伝道誌』合本(一九〇一年正教会刊)にも花巻に正教会伝道所があったことは記載されていない。
岩手の既成の教会は一九一〇年代後半に入るまでこの地方の伝道を殆ど積極的には行っていない。しかし、一九〇〇年代に入って斉藤宗次郎ら少数の無教会派(内村鑑三の聖書研究会)のキリスト者が出て来る。然し積極的な活動はしていない。
浸礼教会(バプテスト)は盛岡をベースに岩手県北への伝道に力を入れていたが、一八九七年遠野の開拓伝道をはじめた。この遠野の夏期伝道で活動した佐藤卯右衛門神学生は牧師となって一九〇六年五月遠野に定住牧会した。
この新進気鋭の佐藤牧師は花巻地方のバプテスト教会の復活に意欲をもち一九〇八年頃から巡回伝道をはじめまた、この派の盛岡の教会(現在の教団の内丸教会)からの教職でない熱心な信徒の篤志伝道も断続的にあった。折からの<大正デモクラシー>の気運は保守的な花巻でも若い人々の間におよびキリスト教会の雰囲気に惹かれ集るようになって来た。高橋慶吾もそういう中の一人であったらしい。
ただ花巻のバプテイスト教会が巡回教会から独立した教会として定着するのは一九三〇年ごろでその基礎作りをしたのは林文太郎牧師、阿部治三郎牧師である。高橋慶吾が出入りし、高瀬露が洗礼を受けたのは佐藤卯右衛門の巡回教会時代である。ただ日本社会の一般的な道徳観にくらべかなり厳しいキリスト教倫理を受け容れ、イエスを受肉せる神子キリストと福音的信仰告白をして受洗に至る者は少なかった。高橋慶吾も信仰には至らないで教会を離れていったのである。
上田哲「「宮澤賢治伝」の再検証(二)ー<悪女>にされた高瀬露ー」 1996(平成8)年
![「猫の事務所」調査書[ファイル0508]](https://ntcj-chousa.com/file0508/wp-content/uploads/2025/05/file0508logo.png)